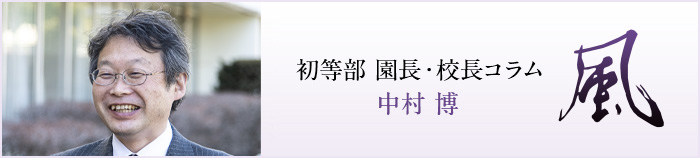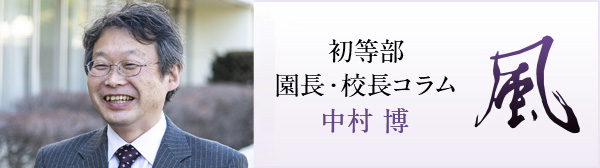ゆっくりとした時間、自由な空間の中で[Ⅱー413]
園庭で過ごせる幸せ
園庭には、プラタナスやソメイヨシノの枝や葉が落ちています。その枝をひろい、魔法の杖として使う人*がいます。時々、魔法をかけられてしまう私。砂場では、枝は砂糖と粉をまぜる棒になります。出来上がったケーキなどをおいしくいただきます。しぜんひろばに行けば、枝は魚つりの釣り竿となり、魚を釣っています。枝は変化します。
砂場は、川をつくり、水を流す人がいます。大きな飾りのたくさんついたケーキをつくる人もいます。川つくりやケーキつくりなど、たのしそうで参加する人が増えます。川の通りをもっと長く、もっと深くすすめていきます。隣では、砂や葉でご飯やおやつをつくっています。
気温の低い日は、「きょうりゅう山」や畑に霜柱ができます。踏むと音がカサッとなり、触るとひんやりとして、踏みたくなる人がたくさんいます。霜柱、氷あつめも盛んです。大きな霜柱や氷を見つけ、手に持つことは冷たいけれども喜びのようです。しぜんひろばの池は凍っている時があり、集めてとり、踏みたくなる人がたくさんいます。
少し前、園庭で焼き芋をしました。マッチを使って火をつけてみました。夢中になって強くこすると火がつく驚き、さらにやってみたい気持ちが膨らむ人がたくさんいます。年少、年中の人たちは、落ち葉や枝を入れてみたくなります。すぐに燃えるモノ、なかなか燃えないモノなど、燃やしてみたいものを持ってきては、先生に相談して燃やしています。自ら試して、変化を捉えて楽しんでいる様子です。落ち葉や葉以外のものでやったらどうなるのか、試したくなります。
*「子どもは何もできないので育ててあげなきゃいけない存在ではなく、子どもは子どもで自分の意思でちゃんと生きている」と、渡辺一枝さんが『子どものしあわせ』2025年1月号で話していました。そう、自分の意思でちゃんと生きている「人」なのだと思います。
共同研究者 久保健太さんが『生命と学びの哲学―育児と保育・教育をつなぐ』(北大路書房)の中で、ドゥルーズの「離脱」の保障について書かれており、この「離脱」をとらえるために、倉橋惣三さんや津守真さんの「自己活動」の思想を述べています。津守さんの「自己活動」を紹介されたところを何回も読んでいます。以下に引用をさせていただきました。
第一に、子どもにゆっくりとした時間を与えることが必要である。自分のやりたいことを見つけるための時間、自分の活動にとどまり、自分が満足して終わるまでの時間である。子どもは自分の活動を充実させる時間をもつことによって、自分自身を形成する。
第二には、自由に活動できる落ち着いた空間をもつことである。幼児が自由に歩きまわり、自分のやり方で物を並べ、動かすことのできる空間を確保することである。家の中、片隅、家の周囲の小さな空間、陽のあたる戸外などで、幼児はゆっくりと自分の活動をする。
第三には、子どもが自分の手足や身体で操作して遊ぶことのできる素材を用意することである。土や水、木の葉などの自然物、紙や鉛筆、積み木や人形などの素朴な玩具、子どもの力で変形し、想像し、多様に使える材料である。
第四には、互いに応答し合う大人や友達の存在である。命令したり指示するのではない。人間らしい自然な応答をする人間的な環境が、何よりもたいせつである。
私は、園庭やしぜんひろばで過ごせる幸せを感じながら、「ゆったりとした時間」や「自由に活動できる落ち着いた空間」、「子どもが自分の手足や身体で操作して遊ぶことのできる素材」、「互いに応答し合う友だち」などをこれからも大切にしたいと思い、現在、津守さんが書かれたことがどれだけできているのかと問い続けています。
お知らせ。前号(412)の後半部分を加筆修正しました。