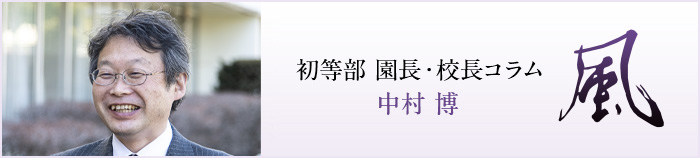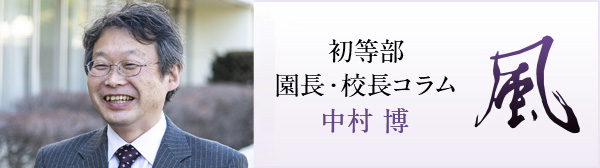桐朋幼稚園のおもちつき [Ⅱー414]
「おもちつきって どんなの?」「やったことないけど やってみたい。」「おもちつき やりたいな!」
年少の人たちは、桐朋幼稚園でのおもちつきは初めて。おもちつきの日に向けて、材料や道具を準備したり、臼や杵に触ってみました。おもちつきの本を読んでもらったり、おもちつきの歌を教えてもらったりしました。年長の人が研いだもち米を見せてもらって、形が丸いことを発見しました。臼と杵をたわしで洗って、準備をすすめました。
秋に園庭で焼き芋をしていたので、火を見たり、あたたまったり、においを嗅いでみたりしています。また、年長や年中の人が火をつけたり、いろいろなものを試して燃やす姿も見ています。年少の人たちも、おもちつきのために、火に入れるため小枝を拾ったりしました。


当日、ふかしたもち米を一人一口ずついただきました。どんなことを感じたのでしょう。
年少の人たちが、杵を持ってついてみました。
「それぞれの子に、この経験が心に残るといいな」と、保育者は願います。


年中や年長の人たちは、これまでの経験があります。
たとえば、もち米をふかすかまどに火を燃やすための薪が必要で、みんなで取りに行きました。施設管理の方が縄で組んでくださった薪を運びます。思っていたよりも「重くない。」「軽い軽い、簡単!」。段々重さが腕にのしかかり、途中で組んでた薪が縄から落ちるなども。こうしたハプニングが、「こうやって持ってみればいいんじゃない、」「俺がここ持つから、そっち持って」など試行錯誤や協同が生まれて、より一緒に運んだ実感を深めてくれたかもしれません。
自分の力で杵を持ってつくように、保育者ははじめから手を添えるようにはしませんでした。足腰に力を入れ、ふんっと杵を持ち上げ、搗いていく子どもたち。実際に手にしてみると思いと感じたのか、「いっしょに持って」と伝えてくる人もいました。困ったときになんとかしよう、助けをもとめることが身についています。
おもちをついている子の周りで見守り、「よいしょ、よいしょ」などのかけ声など、おもちをつくことが「「一人ひとり」と「みんな」の目的として、大人から与えられたものというより、彼らの内側から生まれ出たような感じ」を受けたという保育者。こうした率直な思い、捉えを聞いて、その眼差しに嬉しくなりました。


<もちつき手遊びうた>
年長の人たちは、3回目のもちつきです。手遊び歌を思い出したようです。
「とうほうようちえん もちつきうた」
ぺったん ぺったん おもちつき / とうほうようちえんの おもちつき
ぺったんこ ぺったんこ ぺったん ぺったん ぺったんこ / とん こねて とん こねて とん こね とん こね とん こねて / とっ ついて とっ ついて とっ つい とっ つい とっ ついて
とんとんとん とんとんとん

当日、2階にいる小学生の人たちからも、おもちつきの歌が聞こえてきました。懐かしい、たのしい思いが湧き上がってきたのでしょう。
準備、実際のもちつき(「こづき」や「ちぎり」なども見せていただきました)、片付けと、たくさんの大人の手を借りて、無事に出来ました。皆様、ありがとうございました。
*本文は、「たんぽぽつうしん」「ばらぐみつうしん」「ゆりぐみつうしん」をもとにしました。保育者の眼差し、かかわりに、私自身が学ばせてもらっています。