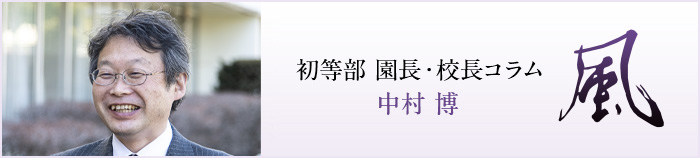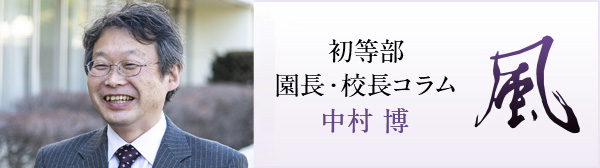「自分が自分であって大丈夫」「生きているだけで周りから肯定される感覚」 [Ⅱー416]
先日の新入生保護者会で、家庭と学校で大事にしていきたいことの一つとして、「自己肯定感」のお話をさせていただきました。それは、故 高垣忠一郎さんより学んだ「自分が自分であって大丈夫」という感覚、「生きているだけで周りから肯定される感覚」です。高垣さんの自己肯定感は、よいところをほめたり、資質、能力を評価して「自己肯定感」を高めるのとは違います。
その話の後で、6年生一人ひとりの卒業期「自分史」の取り組みを紹介させていただきました。お子さんにご家族が心を込めて話してくださり、それはその子その子のかけがえのない命の大切さを伝えてくださっていることで、「生きているだけで周りから肯定される感覚」を感じさせられるものだと思います。
ある人は、「お母さんと一緒にアルバムや育児日記をみながら、私が生まれるまでと赤ちゃんだった頃の話を聞きました。日記には赤ちゃんだった頃の写真や、楽しいエピソードがたくさん詰まっていて、思わず笑顔になりました。お母さんは、私が生まれた日のことや初めて歩いたときのことを楽しそうに話してくれました」と書きはじめていました。話を聞いて「思わず笑顔に」なったり、「楽しそうに話してくれ」ことをうれしく受けとめるなど、幸せな時間だったと思います。私も自分史よりたくさんのことを感じ、学んでいます。読ませていただいて、ありがとうございました。


自分史 お腹にいる時~歩くころまで
[お腹にいる時]
お母さんのお腹にいると分かった時、僕は、三・六ミリでした。でもその時、まわりに血のかたまりができていて、切迫流産と言われ、お母さんは家で安静にしていたそうです。一カ月くらい安静にしていて、病院の先生から/「もう大丈夫ですよ。」/と言われ、心の底からうれしかったと言っていました。毎回病院の健診でエコーの写真をもらっていましたが、生まれるまでずっと顔をお腹のすみによせたり、後ろを向いたりしていたので、生まれ時にやっと顔が分かったそうです。僕はなんで顔を見せなかったんだろうと未だに疑問です。
お母さんは心臓の病気があったので、お腹の中にいる時に僕も検査を受けましたが、病気はなかったのでお父さんもお母さんもほっとしたと教えられました。でも、へそのおがたいばんのまん中ではなく、はじっこについていたので、栄養が十分に僕に行かないかもしれないと先生に言われ、お母さんはそのことをインターネットで調べ過ぎて不安ばかりが強くなったそうです。
[僕が生まれた時]
お母さんの心臓に負担がかかると大変なので、大学病院で計画出産でした。入院した人の夕方四時頃に陣痛が来てお母さんが、/「病院に着いてるのが分かってたのかな?」/と思ったそうです。
その後、心臓が逆流して菌が入らないように、薬を点滴しながら、陣痛をたえていたらしいです。僕が生まれる四十五分前、僕の頭が出るたびに、一分間に一四〇回あった心拍がなんと四十四回くらいまで下がって、低い音で「ドッドッ」と機械からアラーム音が鳴って、病院の先生があわてていたので、お母さんも不安になって、/「このまま赤ちゃんに会えなかったらどうしよう。」/と頭が真っ白になりました。そこで、病院のえらい先生が来て「鉗子」という道具を使って僕の頭をつかんで引っ張り出して、やっと僕が生まれました。一気に引っ張り出さないと心臓が止まってしまう状況だったなんて初めて知ったので、ちょっと怖くなりました。僕が生まれる時、命の危険にさらされてたけれど、医師や助産師の人ががんばって処置をしてくれて生まれたので、あの時つくしてくれた人に感謝したいです。あとお父さん、お母さんがここまで育ててくれたのでこの命を大切にしたいと思いました。/生まれてから分かったことですが、僕の体の下にへそのおがあって圧迫して血の流れが止まりそうになっていたので、心拍が下がったそうです。
[僕が〇才の時]
僕は母乳やミルクをよく飲んで、よくねてニコニコ笑顔が多かったそうです。/僕が初めて歩いたのは〇才十一カ月の時でした。ハイハイで速く移動することが得意でつかまり立ちも早かったそうです。お父さんもお母さんも/「いつ歩き始めるのかな。」/と楽しみにしていましたが、初めの一歩は保育園にいる時でした。その日にお迎えに行くと、先生から、/「今日歩きましたよー!」/と嬉しそうに報告があってお父さんもお母さんも見られなくて残念だったけれど、先生達みんなでよろこべてよい思い出になったと言っていました。僕はその時のことは覚えていないけれど、みんなに見守られながら歩いたと知ってうれしかったです。
[僕の名前の由来]*ここでの内容は、作者の名前がわかってしまうので、掲載できません。
名前の由来を聞いた作者は、そこに込められた願いを受けとって、「もし困っている友達がいれば、力になってあげたいと思っています。」と書いていました。
[感想]
僕は今回、作文を書く前に、僕がお母さんのお腹にいる時の写真やへそのお、生まれた後のアルバムなど、色んな物を見てきましたが、やっぱり僕は、お母さんやお父さん、さらに祖母などに愛情を注がれてここまで成長できたので、僕は自分を大切にしようと思いました。

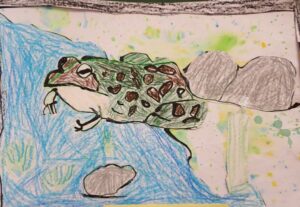
こうした自分史の取り組みは、私たちが大事にしたい「子どもの権利条約」*につながります。子どもは、「あせらず、ゆっくり、たっぷり自分(たち)らしく子ども時代を過ごそう」と願うし、そうした社会にしたい。権利としての「安心」「自信」「自由」などを、ご家族が伝えてくださっていると、私は思います。
*「子どもの権利条約」/1989年、国連総会で採択、日本は1994年に国会で批准し、世界で158番目の締約国となりました。その内容は、
〇「子ども」は、あせらずゆっくりたっぷり自分(たち)らしく子ども時代を過ごそう。
〇「権利」とは、人間として誰もが持っていて当たり前のこと。たとえば、「安心」、「自由」、「自信」など。「安心」とは「心が安らか」で「いのちの危険や病気になっても治療が受けられるなどの不安がな」いこと。「自由」は、「自分の考えが大切にされ、行動できる」こと。「自信」は、「自分のことを価値ある存在として自分自身を認められること」です。


作品は、2月に実施した美術展より