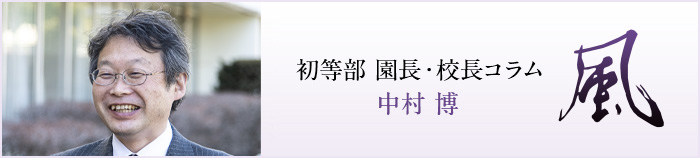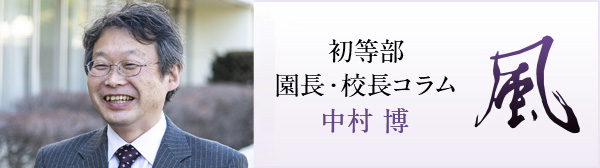桐朋小学校で大切にしたいこと [Ⅱー422]
先週、1学期の始業式、入学式を行いました。昨日は、入園式でした。ご進級、ご入園、ご入学おめでとうございます。
新しい出会い、新しい生活をたのしみにしてきました。入学式を迎え、1年生のパートナーとなった5年生は、はりきっていました。入学式の朝にパートナーとの出あいなど、緊張した人もいたことでしょう。1年生もドキドキしたり、わくわくしたり、いろいろな気持ちを持ったでしょう。出あいを大切に、これからをつくっていきましょう。
入学式では、2年生は学校代表として、桐朋小学校はこういう学校だよと、表現をしてくれました。幼稚園の年中、年長組の人たちは、入園の人たちを迎えて歌を歌ってくれました。1年生との出あいは、在園、在校生にとっても変化、成長の機会となりました。


今週、ご家庭に「桐朋小学校の教育で大切にしたいこと」を配布します。私たちは、子どもの育ちと教育について、目標や大事にしていくことなどを話し合ってきました。そして、10年を目安に、園・学校案内を改訂します。5月に、保護者の皆さんへ新学校案内をお渡しする予定です。その中から、桐朋小学校の教育目標、大切にしたい9の柱をお伝えします。文書に記したことを大切に、子どもたち、保護者の皆さんと日々を過ごしていきます。
■桐朋小学校の教育目標
1 子ども一人ひとりを原点に
子どもたちが「今」を豊かに過ごし、その子らしい生き方を大切にします。「子どもを原点に」という願いのもと、多様な子どもたちをかけがえのない存在だと信じています。
私たちは、子ども一人ひとりを大事にし、心を込めて寄り添います。また、保護者の皆さんと心を通わせ、共に子どもたちを見守り育む関係を築いていきます。
子どもが自分自身と他者の大切さを深く信じ、そのかけがえのなさを理解できることを大切にしています。
2 自分自身の人生の主人公に、そして社会のつくり手となりゆくためのねっこを育てる
一人ひとりが民主的な対話を通じて平和を希求し、社会に参加するためのねっこを育みます。地球環境を守る願いをもち、人権を尊重し、お互いのちがいを認め合いながら、共に生きていきます。地球市民の一員として、子どもたちが社会のつくり手と成長できるよう、その土台を築いていきます。
何よりも、子どもたちにとって居心地のいい場所であることを大切にします。
子どもたちが幸せな小学生時代を過ごすことが、自分の人生を豊かにし、そしてこの社会のつくり手となりゆくねっこを育むことにつながると考えています。


■教育目標を実現するための9の柱
1.学ぶことは楽しい!
子どもの意欲をかき立て、子どもの疑問を大切にします。子ども自ら課題を見つめ、選択して学び続けること、物事を考え、判断し、行動する力を育みます。
2.遊びは最高の学びです
たっぷりと遊ぶことで子どもは心身を耕します。子ども時代に遊びに没頭することで得られる経験は、豊かな人生を送るための肥やしとなります。
3.子どもの自治を大事にします
大事なことを自分たちで決めていく経験は大切です。さまざまな参加を通して社会のつくり手となっていくための根っこを育てます。
4.実際に行う・本物と出あう
自然そのものとのふれあいや、実際に事物にふれて操作することを大切にします。身体をくぐらせた経験が、抽象的な概念や法則化の深い理解を育みます。
5.学びの過程や意味を大切にします
時間がかかっても、試行錯誤や失敗などから、身体でわかることを大切にします。「できた」「わかった」だけでなく、つまずき、まちがい、とまどいも、自分という人間を豊かにします。
6.ともに学ぶ・ともに働く・ともに遊ぶ
子も親も教師も、お互いの良さを大切にする関係を育て、同時に自分らしさを育みます。
7.子どもの発達にあわせた教育課程の自主編成教育を行います
子どもの身近にいる私たちが、芸術や科学の成果を大切にしながら、子どもの発達にあわせた教育課程の自主編成教育を行います。
8.親と教師、親と親は、子どもの「今」と「未来」のために結びあいます
その子その子の成長を見守り、援助することが大人の役割と考えます。子どもの一人ひとりの「最善の利益」とは何かを考え、その実現のために結び合います。
9.子どもも大人も自分らしくいられる学校に
子どもが子どもらしくいられる時間と安心して過ごせる教室空間を大切にします。授業や活動内容に応じて過ごしやすい空間につくりかえる「居心地のいい教室」。ゆったりくつろぐ時間、夢中になって過ごせる放課後を保障します。


朝日新聞4月13日社説に、「探究と未来 面白そうをはぐくもう」という題で、「学校や職場で、次のテストの点数や今月の実績も大事だろうが、将来の高みを目指すには基礎固めや試行錯誤、心ひかれることに熱中するのも大切だ。「すぐに役立つものは、すぐに役立たなくなる」と言われるではないか。/新たな歩みが始まる春、心機一転する人も多いだろう。そんな人たち、そして未来のために、目先にとらわれず、面白さや楽しさを大切にできる社会でありたいと思う。」ということが書かれていました。
4月始業前、子どもの権利について増山均先生(早稲田大名誉教授・日本子どもを守る会会長)から学ぶ機会を職場全体で持ち、
・子どもの権利条約31条に規定されている休息と余暇が保障され、楽しく遊び、想像力を羽ばたかせていく権利、すなわち休息・余暇(気晴らし)権、遊び権、文化権の課題
・子どもの権利条約40条に規定された失敗できる権利、やり直し立ち直っていく権利、更生権保障の課題
・子どもの権利条約12条、15条に規定されているように、自由に意見を出し合い集団的自治的に活動し、自ら集い会い、社会に主体的に参加していく権利(真に生と主人公になるために不可欠の権利)、自治権、社会参加権保障の課題
を実践課題として受けとめました。それから、一人ひとりのしあわせな子ども時代を大事にすることの意味として、「力いっぱい楽しんで 生きる今が しあわせな未来をつくる。」、「遊びは子どもの主食 楽しい子ども時代が輝く人生をつくる。」、「子どもは飽きるほどの自由な時間の中で 自分と出会い やりたいことを見つけ出す。」に共感しました。
新学期を迎えて、深くうなずくことがたくさんあります。*写真はすべて新学期の園、学校の様子からです。