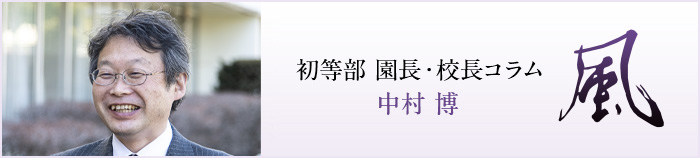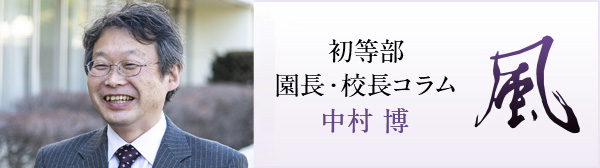命を活き活きと輝かせてチャレンジし続ける卒園生[Ⅱ‐430]
卒園生のTさん(桐朋幼稚園、桐朋小学校、桐朋中学校、桐朋高校を卒業して、現在、九州大学大学院で学ぶ)へ話を伺う機会がありました。Tさんは、ご自身の願いによって、外の世界(人やもの)と自分自身にはたらきかけ、いろいろなことを取り込みながら、新しい自分を創造していました。


「こんにちは卒業生」
チャレンジし続ける 小学校卒業第55期* T・Yさん
〈初等部〉 幼稚園ではとにかく自由でした。したいことを先生に伝えると、一緒に泥だらけになって全力で遊んでくれた印象があります。仲良くなるための喧嘩なら喧嘩スペースを作ってくれたりして。そのおかげでのびのび成長でき自分の基礎を作ることができたと思います。
また、小学校も思い出がたくさんあり、特に味噌を作ったりして発酵をテーマに「発酵食品パーティー」をしたのが印象深いです。担任の先生がすごく活動的で、みんなで食材の育て方から料理の仕方を学んで、料理を囲むのは本当に楽しかったです。
自主学習ノート制度もまた印象的です。当時は本当に勉強が嫌いで宿題とか嫌いでした。そんな中で担任の先生が自主学習ノートを開始、「好きなことを勉強してノート2ページ分書いてきて!」って。自分は初めての自主学習ノートで「世界の標高の高い山」について調べたんですけど、それでも「よく調べたね。学びになったね。」って伝えてくれて。社会とか特に嫌いだったんですけど、今ではそれが学ぶ楽しさを知るきっかけになったんじゃないかなって思ってます。
*2025年3月現在、卒業は66期
〈中高時代〉 めっちゃ楽しかったです。男子校ならではの楽しさが凝縮されてて、同級生だけじゃなくて先生との思い出もたくさんある6年間でした。
また、中学の修学旅行で東北の被災地を訪れたとき、津波の映像やその津波の傷跡を見てすごく衝撃だったのは今でも忘れられないです。その時に人々を助けるような仕事がしたいなあってなんとなく思ったんですよね。
そうしたら高校生の時に電車で見たJICAの広告で、きれいな飲み水がない地域があること知って、工学に興味があったことも相まって「これだ!」って。自分なら井戸を作ることで手助けをできるかもしれないって思ったんです。それを軸として大学を選んで入学しました。
〈大学時代〉 自分の通っていた学科が海外との結びつきが強いっていうのもあって、海外に行くことが増えました。それまであまり海外って行ったことなくて。
特にその中でもJICAのボランティア派遣体験プログラムに参加したときにガーナに行ったんですけど、この三週間の経験は印象深くて、とてもいい経験になりました。
現地の人に話を聞いたり、実際の市場とかを見て、課題や改善点を自分たちで見つけ出して、現地のNPOとJICAの人から毎日フィードバックをもらいながら、解決策を自分たちで考え出して提案するみたいなことをしました。しかし、生活水準や衛生環境はそう簡単に変えられない、こんなにも何もできないのかっていう無力感を感じてしまうことが多かったり、自分たちは4人1組で日本人同士支え合っているからできたけど、一人でやるってなったらしんどいのかなって思いました。
それでも、これをしなかったら、ちょっとずつしていかなかったら何も変わらないとも思いました。このような経験から、今では海外と関わりの強い専攻を選択し、将来もそんな仕事に携われるように学び、活動しています。
桐朋教育研究所発行『桐朋教育』(2025年7月発行予定)「こんにちは卒業生」より

誌面の都合から、記事では概要をお伝えしています。
記事に関連した語りに少し触れると、「教室で味噌とか作って、びっくりしましたね。カビとか入ってて。『あ、こんなん食えねえじゃん』と思ったり…。だけど、カビを取ってどんどん発酵させていくとか、なんかいろいろ面白くなって…」(小)、
「小学校の時に野球をちょっとやってて、見逃し三振とか空振り三振した時に悔しすぎて、悔しいけどその怒りをボールにぶつけろとか言われたんですけど、当たらないからぶつけられないし、どうすればいいんだろうと思って。それだったら、もっと直接たたかうような柔道とかラグビーとかにしよう。それで負けたら本当に自分の実力不足だなって諦めがつくかなと思って。柔道とラグビーで迷った時に、個人スポーツだと努力しなくても試合に出れるけど、集団スポーツだと努力しないと試合に出れないぞって、親から言われて、ラグビー選んだって感じでしたね」(中)
など、その時々の感動、熟考、選択がとても豊かでした。
Tさんは保護者から、「『勉強をしなさい』と言われた印象はほとんどない」と言っていました。先ほど「柔道とラグビーで迷った時」のことで触れましたが、ご自身が迷ったり困ったりした時に、親の考えを聞いて、自分で考え決めたことを言われていました。
Tさんの親御さんは、自分で間違えたり、失敗したり、行きつ戻りつしながら成長していく人間観をお持ちで、ゆったりした関わりをされていると、私は捉えています。
Tさんのお話全体から、迷いやとまどいも含めてその瞬間を充実して生きること、その積み重ねが自由に、幸せに生きることにつながること、心をやわらかくして自分の気持ちに正直であること、芯となるものをつかみ、磨くことなどを大切にしていると捉えました。
私たちは、保育、教育において「生涯を通しての自己実現のための素地の形成を援助する」ことを大切にしていますが、「素地を形成を援助する」ためには、先取りや、目先のための学びではなく、今この幼児期、児童期でなければ学んだり、身につけたりすることが出来ないことを子どもたちに示したいと、Tさんのお話を伺い、あらためて思いました。
 写真はすべて先週の様子から
写真はすべて先週の様子から