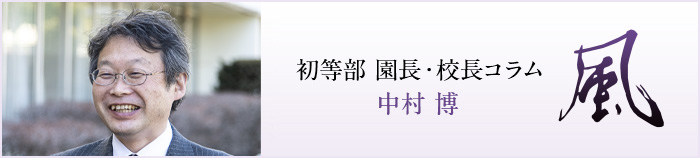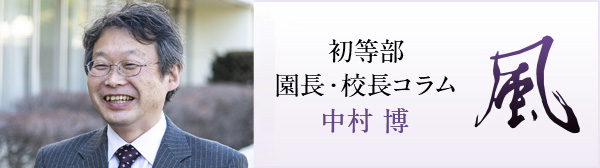長崎平和宣言 [Ⅱ-433]
雨風が続いています。大雨による大きな被害が伝わり、被害にあわれた方がたくさんいます。九州に住む友人から、「大雨で自宅缶詰。土砂崩れや
戦争が続いています。戦争で亡くなる子ども、飢えて亡くなった子どもの映像を見ます。この事実を知ろうとしなくてはいけないと思うのです。
 桐朋小6年生 広島修学旅行
桐朋小6年生 広島修学旅行
8月9日、長崎市長の平和宣言を聞きました。その後、平和宣言を写して読みました。毎年、しっかり読むようになったのは、2009年、長崎で土山秀夫さん(被爆者、医者)とお会いしてからです。土山さんは、平和への強い思いを伝えてくださいました。土山さんと出会って、土山さんが平和宣言の起草委員を務められていることを知り、平和宣言を学び考えていこうと思いました。
2025年平和宣言は、「対立と分断の悪循環で、各地で紛争が激化」し、「人類存亡の危機が、地球で暮らす私たち一人ひとりに、差し迫っている」と書かれています。
桐朋学園初等部で大切に使っている「地球市民」ということばも出てきます。宣言には、地球市民として、「人種や国境などの垣根を越え、地球という大きな一つのまちの住民として、ともに平和な未来を築いていこうという思い」が込められていました。
NHKのニュースでは、今回の平和宣言の特徴として、「紛争をしている人たちに対して武力による争いを今すぐやめるように求め、核兵器が存在するかぎり、誰もが核兵器の脅威にさらされる「当事者」であることを強調」、「長崎の被爆者が大切にしている人種や国などの違いを超えた「地球市民」という視点を新たに盛り込み、「地球市民」として対話を重ねることで分断を乗り越えていく」ことが書かれていました。
以下、原文を写しました。
1945年8月9日、このまちに原子爆弾が投下されました。あの日から80年を迎える今、こんな世界になってしまうと、誰が想像したでしょうか。
「武力には武力を」の争いを今すぐやめてください。対立と分断の悪循環で、各地で紛争が激化しています。
このままでは、核戦争に突き進んでしまうー。そんな人類存亡の危機が、地球で暮らす私たち一人ひとりに、差し迫っているのです。
1982年、国連本部で被爆者として初めて演説した故・山口仙二さんは、当時の惨状をこう語っています。
「私の周りには目の玉が飛び出したり 木ギレやガラスがつきささった人、首が半分切れた赤ん坊を抱きしめ泣き狂っている若いお母さん 右にも 左にも 石ころのように死体がころがっていました」
そして、演説の最後に、自らの傷をさらけ出しながら、世界に向けて力強く訴えました。
「私の顔や手をよく見てください。世界の人々 そしてこれから生まれてくる子どもたちに私たち被爆者のような 核兵器による死と苦しみを たとえ一人たりさも許してはならないのであります」
「ノー・モア・ヒロシマ ノー・モア・ナガサキ ノー・モア・ウォー ノー・モア・ヒバクシャ」
この心の底からの叫びは、被爆者の思いの結晶そのものです。
証言の力で世界を動かしてきた、被爆者たちの揺るがぬ信念、そして、その行動が評価され、昨年、日本被団協がノーベル平和賞を受賞しました。日本被団協が結成されたのは、1956年。心と体に深い傷を負い、差別や困窮にもがき苦しむ中、「自らを救うとともに、私たちの体験をとおして人類の危機を救おう」という結成宣言をもって、長崎で立ち上がりました。
「人類は核兵器をなくすことができる」。強い希望を胸に、声を上げ続けた被爆者の姿に、多くの市民が共感し、やがて長崎に「地球市民」という言葉が根付きました。この言葉には、人種や国境などの垣根を越え、地球という大きな一つのまちの住民として、ともに平和な未来を築いていこうという思いが込められています。
この「地球市民」の視点こそ、分断された世界をつなぎ直す原動力となるのではないでしょうか。
地球市民である、世界中の皆さん。
たとえ一人ひとりの力は小さくとも、それが結集すれば、未来を切り拓く大きな力になります。被爆者は、行動でそう示してきました。
はじめの一歩は、相手を知ることです。対話や交流を重ね、互いに理解し、小さな信頼を重ねていく。これは、私たち市民社会の大きな役割です。
私たちには、世界共通の言語ともいえるスポーツや芸術を通じて、また、発達した通信手段を使って、地球規模で交流する機会が広がっています。
今、長崎で、世界約8500都市からなる平和主張会議の総会を開いています。市民に最も身近な政府である自治体も絆を深め、連帯の輪を広げています。
地球市民として、共感と信頼を積み重ね、平和をつくる力に変えていきましょう。
地球市民の一員である、すべての国の指導者の皆さん。
今年は、「戦争の惨禍を繰り返さない」という決意のもと、国連が創設されてから80年の節目でもあります。今こそ、その礎である国連憲章の理念に立ち返り、多国間主義や法の支配を取り戻してください。
来年開催される核不拡散条約(NPT)再検討会議は、人類の命運を左右する正念場を迎えます。長崎を最後の被爆地とするためには、核兵器廃絶を実現する具体的な道筋を示すことが不可欠です。先延ばしは、もはや許されません。
唯一の戦争被爆国である日本政府に訴えます。
憲法の平和の理念と非核三原則を堅持し、一日も早く核兵器禁止条約へ署名・批准してください。そのためにも、北東アジア非核兵器地帯構想などを通じて、核抑止に頼らない安全保障政策への転換に向け、リーダーシップを発揮してください。
平均年齢が86歳を超えた被爆者に、寝越された時間は多くありません。被爆者の援護のさらなる充実と、いまだ被爆者として認められていない被爆体験者の一刻も早い救済を強く要請します。
原子爆弾で亡くなられた方々とすべての戦争犠牲者に、心から哀悼の誠を捧げます。
被爆80年にあたり、長崎の使命として、世界中で受け継ぐべき人類共通の遺産である被爆の記憶を国内外に伝え続ける決意です。永遠に「長崎を最後の被爆地に」するために、地球市民の皆さんと手を携え、核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に力を尽くしていくことをここに宣言します。

8月5日『東京新聞』(上記)に、広島市の被爆者 笠岡貞江さん(92)の記事が掲載されていました。笠岡さんには、数年前から、桐朋小学校6年生の広島修学旅行で証言を聞いています。
以下、新聞記事を写しました。
原爆投下で両親を亡くした広島市の被爆者笠岡貞江さん(92)は、20年前から「被爆体験証言者」として国内外で核兵器の恐ろしさを語り続けてきた。「核兵器を使えば世界が滅亡する」。笠岡さんの体験や、平和への思いを引き継ぐ「被爆体験伝承者」は27人になった。
1945年8月6日、両親は早朝から空襲に備えて家屋を壊す建物疎開の作業に出かけていた。笠岡さんは爆心地から約3.5キロ離れた自宅にいた。洗濯物を干して部屋に入ると、光が見え、風圧で飛ばされた。気が付くと頭から血が出ていた。
爆心地から約2キロの場所から帰ってきた近所の人は、皮膚が垂れ下がり「広島は大ごとじゃ。ピカッと光ってみんなやられた」と言った。
父は親戚の家にいることが分かり、翌朝、兄が連れて帰った。やけどで全身が真っ黒になった父は本人なのかどうかも分からない。「キュウリやジャガイモを擦りおろしたものを塗るぐらいしかできなかった」。好きだったビールを飲ませても、口からこぼれ落ちるだけだった。
逃げる途中ではぐれた母や、学童疎開中の弟を心配し「頼む、頼む」と言って8日に息を引き取った。
母は、多くの負傷者が搬送された広島湾の似島にいた。兄が名簿を確認すると、父と同じ日に亡くなる火葬されていた。残ったのは、遺髪と遺骨が入った袋だけ。「学童疎開から帰ってきた弟は、仏壇を見てぼうぜんと立ち尽くしていた」
翌年になって笠岡さんの体には吹き出物ができ、膿が出た。治るまで約半年かかった。高校卒業後は広島県庁に勤務。結婚し2人の子どもに恵まれたが、被爆者の夫はがんを患って35歳で亡くなり、幼い子どもを抱えながら働いた。
被爆体験を初めて話したのは孫の小学校。文章や絵で自分の思いを上手に伝える児童の姿に感銘を受け、2005年に広島市の被爆体験証言者になった。「戦争や核兵器はいけん、という力が市民から上がってほしい」と国内外で話している。
今は30~80代の27人が笠岡さんの伝承者として活動する。「皆さん熱心。私がいなくなっても伝えてくれる人がいて幸せ」。笠岡さん自身も今月11日から米ハワイ州を訪れ、現地の学校などで証言する予定だ。「原爆を知らない人に知ってもらいたい。二度とあってはいけないことだから」
 笠岡さんの証言をお聞きして(広島修学旅行)
笠岡さんの証言をお聞きして(広島修学旅行)