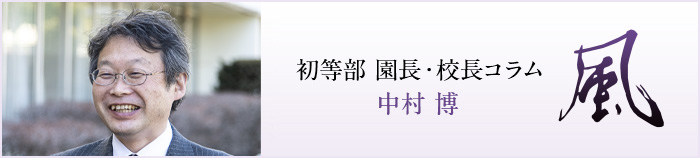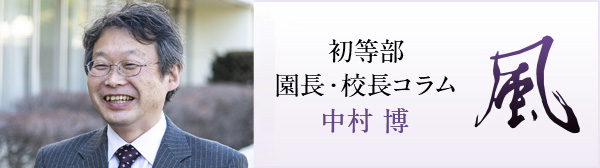2025年、どうぞよろしくお願いします [Ⅱ-412]
1、3学期の始業式
子どもたちとの出会い。子ども心に、たのしそう、やってみたい気もちを少しでも持ってほしい。そうした願いを持って、子どもたちとの出会い、過ごす時間をたのしみにしていました。
【へびどし】《アクロスティック》で、新年の願いを伝えることにしました。
へ →《〈へ〉いわをひろげる》
ガザやウクライナの人たちの平和を願って。世界の子どもたちの平和を願って。
平和っていうと、とても大きなことを考えるかもしれないけれど、始業式のはじめ、交通安全の方からの話にあった「みんなが気持ちよく過ごせるように」も平和につながるし、次に6年生6人が「小学校時代の思い出」を話してくれて、みんなで笑ったり、しんみりとした気持ちになったり、いろいろな気持ちになったことも平和だからこそ! こうした時間を大切にするのも平和につながっていく。
び →《〈び〉じゅつを味わう》
すぐに1年生から「食べるの?」と聞かれました。卒業生の作品を2つ借りて、「(味わうって)こんなふうに表現してくれた作品を見て、触って、感じることがたのしい(こと)。」と伝えました。美術を芸術と広く捉えています。
2月の全校美術展に向けて、どんな表現をするのかたのしみです。高学年の人たちには、自分の作品をつくるために、知識や技術、技能をどんどん磨いて、自分らしい表現を高めてほしいと伝えました。
ど → 〈と〉にかえて、《〈ト〉ライを》
挑戦してみよう。一人ひとりが自分の願いによって、外の世界(人やもの)と自分自身にはたらきかけ、いろいろなことを取り込みながら新しい自分を創造する、発達の主人公ですから。その挑戦を支えていきたい。
し →《トライを》に続けて《〈し〉よう》
〈し〉に込めたのは、試行錯誤や失敗もとても大切。安心して新たなことに挑戦しよう!
子どもたちは、【へ、び、ど、し】で、どんなことばが続くのかをたのしみに、予想して、その時間を味わってくれているのが伝わりました。
このようなやりとりが出来たのは、ぼくの前に話してくれた6年生その人その人の表現がすてきで、それに大いに触発されたからだと思います。
《トライをしよう》ということで、大人3人で「ベーゴマ」をやってみました。昨日ベーゴマをやってみたいと思い、挑戦した先生。気持ちと行動がすごい! もう1人の先生に教わり、何回か挑戦してまわせる喜びを味わったことと思います。教えた先生は、すばらしい腕前で、丁寧に教え、支えてくれました。さすがだなと思いました。そして私は約50年前を思い出しながら、絶対負けないぞ! という気持ちでやりました。
1月、子どもたちに呼びかけて、「ベーゴマで遊ぼう!」をやってみたいです。
今年も、子どもたちと学びも遊びも夢中になって、たのしんで成長できたらと思います。
2、命を輝かせたい、平和な世界を実現したい
1941 年、「教育こそ永遠である」と考えた山下亀三郎氏が私財を寄付され、第一山水中学校(国立)、山水高等女学校(仙川)が開設されました。そして、1947年に桐朋学園として再出発し、2025年、創立84年を迎えました。
桐朋学園の教育理念は、「一人ひとりの人格を尊重し、自主性を養い、個性を伸長する、ヒューマニズム に立つ『人間教育』」です。初代理事長・校長の務台理作氏が、1947年制定の教育基本法(以下、1947教基法)に深く関わり、学園の教育理念に1947教基法の精神を据えました。1947教基法は、「日本国憲法の精神に則り」、「民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しよう」(前文)としました。そして「この理想の実現は根本において教育の力にまつべき」(同)と記されています。
私たちは、保育、教育を通して、日本国憲法の基本理念である国民主権、基本的人権、平和主義を土台に『生存権としての学習権』を守り育て、みんなが幸せで平和な世界の形成を目指します。このような大きな目標〈理想〉として持ち、実践を続けています。
初等部は、2025年11月、創立70周年を迎えます。11月20日の創立記念日には、子どもたちと一緒に、初等部の70歳のお祝いをします。遊びを通して子どもたちが豊かな力を育むことを大切に考え、子どもたちが平和な社会で遊ぶことのできる権利、子どもたちの遊ぶ力と自由な時間と遊び場(環境)を、過去から現在そして未来に引き継いでいけるような行事をつくります。
この10年の歩みを振り返り、未来につなげます。例えば、2018年より3年保育をはじめ、異年齢で遊び、学び育ち合う子どもの姿に、多様であることの豊かさを感じてきました。2019年、新しぜんひろばを子どもたちと創設。幼小の交わりが深まるなど、人間発達の可能性を広げています。2020年、地球市民の時間を創設。子どもたちが地球市民として、世界の平和や持続可能な未来のために考え行動できる人に育つ、その土台となる学びをすすめています。そうしたものをさらに発展させる、80周年に向かう10年間を創りたい、そのための日々を大切にします。
私たちの地球では、気候変動危機、生物多様性喪失、戦争など、地球規模で破壊が進行し、このままでは持続不可能なことになってしまう可能性があります。なんとしてもくいとめ、未来につないでいかなければなりません。2025 年、世界の、人類の、私たちの課題と向き合い、保育、教育から創造的な挑戦をしていきたいと思います。「理想の実現は、根本において教育の力にまつべき」に、私たちは応えていく努力を重ねます。
皆様と話し合い、協力して、よい年にしたいです。どうぞよろしくお願いします。