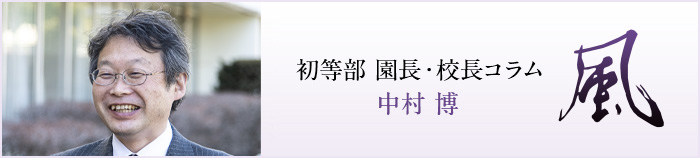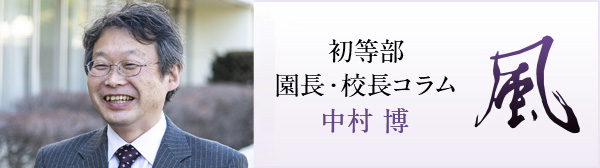春を迎えて [Ⅱー417]
1、2024年度もたくさんの人と出会い、学びました
6年生と私たちに、東京大空襲の体験を話してくださった元木キサ子さん(本校関係者)や竹内静代さん(3月12日東京新聞に記事が掲載)、皆さん、広島修学旅行で証言をしてくださった笠岡貞江さん、碑巡りをしてくださった山岡美知子さん(被爆体験伝承者1期生)、皆さん。大久野島で毒ガス製造の加害、被害について話してくださった山内正之さん。その後もいろいろな方と出会い、学んできました。先日は、車椅子インフルエンサ―の中嶋涼子さん。たくさんの方に支えられ、励まされ、命のバトンを引き継ぎました。ありがとうございました。

今回、今年度も共同研究者として来園され、いろいろと学んだ久保健太さんについて書きます。久保さんには、2016年度より共同研究をお願いしてきました。2018年度より実施した3年保育において、子ども観、保育観、園づくりなど、たくさんのことを学んできました。ありがとうございました。
久保さんは、現在、大妻女子大学で学生たちと学び、桐朋幼稚園で共同研究を続け、横浜で子育て支援者たちとの工夫を重ね、大日向小中学校(日本で初めてのイエナプラン教育に基づく学校)の理事を務めるなど、活き活きと過ごし、「命と学びの哲学」を探究されています。

ここからは、久保さんの本『生命と学びの哲学―育児と保育・教育をつなぐ』(北大路書房、2024年)を少しご紹介する形で、学んでいることを書きます。
現在、教育において、授業や指導のマニュアル化、数値化が進み、結果重視、成果主義の徹底などが進行する中、「同質化」や「均質化」ではない子どもの育ちとは、保育、教育とは、などの根っこを久保健太さんの著書に学んでいます。
久保さんは、青年期の終り頃、葛藤の最中に生活綴方を探究された大田堯さん*と出会いました。大田さんから「失敗や葛藤を、人間の成長にしっかりと位置づけること」を学んで、エリク・H・エリクソンら先達らの理論、思想に深く学び続け、人間発達における葛藤の大事さなどを本書で描きます。本書は柔らかい文体で、ご自身の理論、思想を綴り、育児日記や子どもの写真とエピソードなども多数あって、抽象的にならず深く学ぶ、考えることができます。
本書の章立てです。
序章 生命の教育学
第Ⅰ部 世界の奥行きが、人間に火をつける 葛藤の中で、間違えながら、人は育つ
第1章 自然・生活・学びをめぐって /第2章 「主体的・対話的で深い学び」をキーワードに /第3章 日常生活と民主主義と教育をつなぐ理論
第Ⅱ部 世界が動き、人が試みるとき、そこに学びが生まれる
第4章 乳幼児の学びの理論としてのドゥルーズ/ガタリ理論 /第5章 遊びの語り方を変えよう /第6章 感覚が湧き出ちゃうし、収まっちゃうときの主体性 /第7章 「ちがう」「かかわる」「かわる」に込められた教育思想 /終章 倫理・手のひら・民主主義
全体を貫いているキーワードは、「主体性」「基本的信頼」「自己決定(自己発揮、自己主張)」「自主性(主導権)」「奥行き」「センスーその人にとっての世界の意味、感覚的な意味」「センス・オブ・ワンダーー奥行きに感応しちゃう驚き心」など。そうした世界観を背景に持ち、子どもの育ちや学びを意味づけています。
私は久保さんから学んできて、幼稚園や小学生の人たちが失敗を繰り返し、試行錯誤して、成功に近づいていく姿に、その背景にはできなくたって見放されない、基本的信頼があることを捉えられるようになりました。この感覚がある人は、安心して挑戦をくり返しています。学ぶことで、子ども観がひろがりました。
久保さんの人間観、学習観は、人間だから「つまずき」「まちがい」「ゆきどまり」「とまどい」が起こり、それらを経て、自分という人間を太らせていく、それが「学び(学習)」というもの。また、「学習者たちが世界(環境、事物)から自分たちなりの意味(センス)を感受することも重視し、そうして感受した意味をも知識として認めるものにしていきたい」と願い、「新しい学び観」として、「世界の奥行を「センス」として感受することを「学び」として重視する、そのような提案が教育哲学の分野では生まれてきています」などを述べています。このような学習観は、私が大切に学んできた生活綴方教育の思想(子どもは表現を通して、自らを変化、成長させていく主体者。表現を通してつながり合う仲間)、実践とつながり、大切にしていくものと捉えています。。
*大田堯さんは、ご自身の教育観を変えたのが生活綴方だと言われ、生活綴方の思想、「生活綴方における「生活と表現」―佐々木昂の仕事をふり返りながら」などを書かれています。参考 大田堯自撰集成全4巻、藤原書店、2014年


2、春を迎えて
私は、谷川俊太郎さんがお書きになったものを読むのが好きです。これまで、谷川さんの詩を味わってきました。節目節目に、好きな詩を味わいます。
この後に紹介する「かすかな光へ」(一部分)は、桐朋幼稚園、桐朋小学校で出あった人たち、他で出あった人たちの姿と重なるのです。
何故、どうして、…、
知りたがり、問いつづけ、…、生きる、学び続ける。
その人その人が、命を活き活きと輝かせて生きています。
春を迎え、子どもたちとの日々を思い返し、「かすかな光へ」を読みました。
かすかな光へ
谷川 俊太郎
あかんぼは歯のない口でなめる
やわらかい小さな手でさわる
なめることさわることのうちに
すでに学びがひそんでいて
あかんぼは嬉しそうに笑っている
言葉より先に文字よりも前に
波立つ心にささやかな何故?が芽ばえる
何故どうしての木は枝葉を茂らせ
花を咲かせ四方八方根をはって
決して枯れずに実りを待つ
この後も、子どもと学びについて書かれているなと、私は読みました。ぜひ、全文を味わってみてください。


11月より学園全体の仕事を担うこととなって、幼稚園で過ごす時間が少なくなりました。寂しさを感じ、かけがえのない大切な場だと、あらためて気づかされました。
それから数か月、『園児や児童、生徒、学生一人ひとりの人格を尊重し、自主性を養い、個性を伸長するヒューマニズムに立つ「人間教育」』を少しでもすすめられるようにと、微力を尽くしてきました。
3月に、この学園で変化、成長した人たちが、未来に向かい羽ばたいていくことを願って応援します。
1年間、お世話になりました。ありがとうございました。*写真は、3月の園、学校の様子から