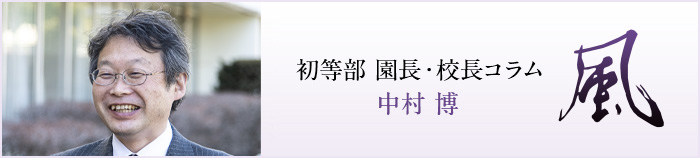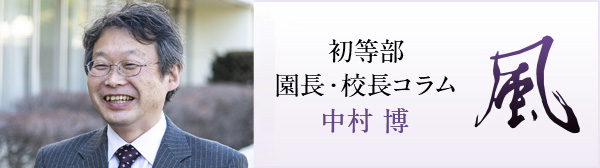2025年度―戦後80年、初等部創立70年を迎えて [Ⅱー423]
2025年度のはじまりに、これまで何度も述べてきたことを書きます。少しでも実現させていく願いを込めて。

1、桐朋の原点
桐朋という学校、桐朋教育は、1947年教育基本法を原点にしています。この法の制定に中心としてかかわったのが、当時の東京文理科大学(のちの東京教育大学)学長の務台理作先生です。先生は、1947年4月に、国立の桐朋第一中学校、仙川の桐朋第二中学校の両初代校長に就任されました。
それから桐朋という学校は、1947年教育基本法の精神、「一人ひとりの人格を尊重し、自主性を養い、個性を伸長するヒューマニズムに立つ『人間教育』」を教育理念に据えて、実践を行ってきました。
1947年教育基本法は、「われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。」と書かれています。「教育の力」にまつべき目標とは、「個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成」、「普遍的にして個性ゆたかな文化の創造をめざす教育の普及徹底」です。
小柳敏志前理事長は、1947年教育基本法で示された理念を、「時代が変わろうとも、色あせない、大事なもの、普遍性があると考えています」と述べていました。小柳先生をはじめたくさんの先生方から学び、私もそう考えます。
2025年度、桐朋の原点にたちかえり、保育、教育を充実させていく年にしていきたいです。

2、戦後の原点
戦後の原点は、アジア・太平洋戦争の反省から、■民主主義(国民主権と基本的人権の尊重)―一人ひとりが主人公、一人ひとりを大切にする。■不戦(平和主義、国際協調)国際紛争を解決する手段としては、武力の行使を、永久に放棄する。戦力を保持しない。■個の尊重(個人の成熟)―一人ひとりが自分の頭で考え判断する。成熟した個人として、さまざまな人と手を携え、世の中の矛盾、問題点に立ち向かう。社会は個人を尊重する。この3つを大切にしました。前理事長の小柳先生より、何回も聞いてきました。
しかし、現在はどうでしょうか。■民主主義(国民主権と基本的人権の尊重) ■不戦(平和主義、国際協調) ■個の尊重(個人の成熟) を大切にして、不断の努力を積み重ねているかと考えます。「安全保障」の名のもと、防衛費は大幅に増加し、核兵器禁止条約は批准しておらず、国際紛争はひろがっています。また、人権の保障が進んでいない(国内人権機関の不在。LGBTQに対する差別を禁止する法律がない。難民認定率の低さなど)ことや勧告(国連子どもの権利委員会から日本への勧告など)を受けることが続きます。
戦後の原点に立ちかえり、「教育の力」で、3つの柱を少しでもすすめていく年にしていきたいです。

3、初等部創立70年
初等部は、創立70年を迎えます。これまでお世話になった皆様へ感謝を申し上げます。
創立70周年を迎えるにあたり、初等部では全員で、これまでの保育、教育を振り返り、今後の保育、教育でだいじにしたいことを全員で話し合ってきました。その内容を新園案内、新学校案内に込めました。
新園案内では、「私たちは、大きな願いとして、保育を通して命を大切にする幸せな世界を、地球を大切にする平和な世界を、築いていきたいと思います。」、「気候変動と呼ばれるこの状況が続けば、生態系が壊れ、日常生活の基盤が崩れる危険性があります。私たちは、これからの『地球』のこと、『未来』のことを考えていかねばなりません。」など、地球市民としての願いも記しました。
新学校案内では、子どもたちがこれから生きる社会、世界を、平和で幸せなものになっていくようにしたいと願い、「一人ひとりが民主的な対話を通じて平和を希求し、社会に参加するための根っこを育みます。地球環境を守る願いをもち、人権を尊重し、お互いのちがいを認め合いながら、共に生きていきます。地球市民の一員として、社会のつくり手へと成長させるよう、その土台を築いていきます」と記しました。
そのことを実現するための〔柱〕として、「学ぶことは楽しい!」、「遊びは最高の学び」、「自治を大事に」、「実際に行う・本物と出会う」、「学びの過程や意味を大切に」、「ともに学ぶ・ともに働く・ともに遊ぶ」、「子どもの発達に合わせた教育過程の自主編成教育を」、「親と教師、親と親は、子どもの「今」と「未来」のために結び合う」、「子どもも大人も自分らしくいられる学校に」を大切に、実践と研究をすすめていきます。

4、保育、教育の原点は、子ども
初等部の教育目標の1つです。一人ひとりを大切にし、寄り添う保育、教育の実現です。一人ひとりのかけがえのなさ、違いを大事に、「ともに学ぶ・ともに働く・ともに遊ぶ」ことを通して、一人ひとりが変化、成長していく姿を励まします。
2年生が、『とびうおのぼうやはびょうきです』を学び、戦争と平和について考えました。その感想からです。(原文ママ)
私は、平和はシンプルに争いがないことでもあると思うけど、かなしいとか、うれしいとか、つらいとか、たのしいとか、ぜんぶをぜんいんがちゃんとかんじられることでもあると思う。
だから私はおこられればかなしくて、べんきょうはつらくて、にちじょうで、いろんなかんじょうをちゃんと心でかんじられる私はすーーーごく幸せ物だなー。て思うよ。
だからまとめると、私からしての平和はいろいろなかんじょうをもてることだと思う。

一人ひとりの気持ちや考えを学級全体で交流し、平和についての考えが深まり、一人ひとりが豊かになったそうです。
平和について、いろいろ気持ちを「ちゃんと感じられることでもある」こと、「いろんなかんじょうをちゃんと心でかんじられる私はすーーごく幸せ物」と自己を捉えていること、「平和はいろんなかんじょうをもてることだと思う」などの考えに、私も学びました。
今年度も、一人ひとりの自由な自己表現を励まし、その表現を寄りあわせ、豊かな学び、遊び、生活をつくっていくことを大切に取り組みます。子ども一人ひとりが、今という時間を充実して生きることを願っています。
皆様、今年度も見守ってください。どうぞよろしくお願いします。

写真は、美術の授業、しぜんひろばでの1年生と5年生パートナー、低学年玄関前の満開のサトザクラです。