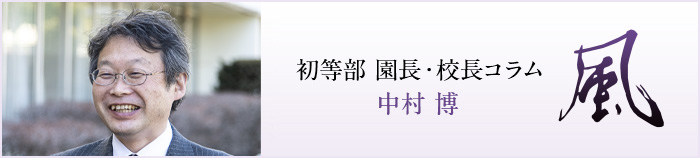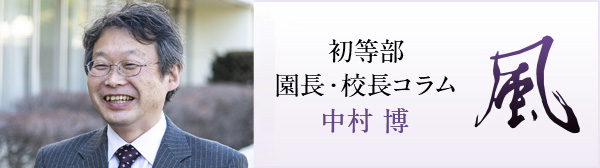6年生八ヶ岳合宿 [Ⅱ-426]
5月21日~23日、山梨県北杜市にある桐朋学園八ヶ岳高原寮(標高1150m)で、6年生が合宿を行いました。お天気に恵まれ、予定していた活動をすべて行うことができました。たくさんの方にお世話になり、ありがとうございました。


主な活動は、自然の中の自由時間(余暇・余白を大事に)、ナイトプログラム、朝散歩(ネイチャーリーダーが、自然と触れ合える企画を考え、実行)、チャレンジプログラム、火おこしをして野外料理、夜の集い(リーダーに内容を任せる。アンケートをとり、話し合った結果、キャンプファイヤーとキャンドルサービスの合体版。点火の劇は4、5年生から続くシリーズもの)、大掃除(掃除当番表をケアクリリーダーが作成)などでした。ナイトプログラム、チャレンジプログラムでは、講師の甲斐崎さんにたいへんお世話になり、ありがとうございました。
この学年のテーマは、「やりたがる!」。4年合宿時の合言葉は「おもしろがる!」、5年合宿時の合言葉は「つながる!」。4年で培った「おもしろがる」精神と、5年からの「つながる」経験を生かして、6年は「やりたがる!」を合言葉に、自分たちでいろんなチャレンジをしていけることを願ってのものでした。「やりたがる!」には、「決められたり指示されたりするのではなく『任される』なかで合宿を自分たちでつくっていこうと思えること、自分自身にとってのチャレンジすること(自分のココロとアタマで自己決定をすること)、みんなのために動くこと」などの意味を込めていました(6年生の先生たち)。
最後の八ヶ岳、おもいっきり たのしもう!! という気持ちで過ごしました。


コラムでは、新たな試み《ナイトプログラム『ナイトアウェアネスウォーク』》と《チャレンジプログラム『ロゲイニング』》を取り上げます。自然豊かな場所で、自分に向き合い、仲間とともに、自然を味わい、冒険する内容でした。子どもたちとともに、「おもしろがる」「つながる」を大切にして、「やりたがる」気持ちを育むものであり、先生たち自身が学びながら、活動内容や方法を自由に創造的に組織していることの大事さに、私自身が学びました。
《『ナイトアウェアネスウォーク』》は、1クラス36名が、12名ずつ3チームに分かれて、寮の敷地の林の中に入ります。1(2)名ずつ灯りに向かって歩いていきます。下の写真は、ナイトアウェアネスウォークに向かう直前、寮内での様子です。

各グループで分かれ、真っ暗な林の中を進みます。スタート地点から、1(2)名ずつ約50m先の灯りを目指して歩いていきます。目印は先に見える灯りのみ。静かな森の中、手足の触覚、葉などに触れた時の音、聴覚などをたよりにすすみました。風の流れる感じや林の中の匂いもします。鹿の鳴き声も聞こえてきました。全員が灯りに辿り着いたところで、目印の灯りを消して暗くして見上げると、空が明るく見えました。昔の人たちは、こうした夜を過ごしてきたことも考えました。
*八ヶ岳からの帰りの電車で、俵万智さんの『生きる言葉』(新潮新書)を読みました。その中に、「自然の中で『めいっぱい遊ぶ』」があって、「(子ども時代は)五感を刺激されることで、成長してゆく時期」、「五感をフルに活用することは、言葉を鍛える土台のようなものではないか」、「『めいっぱい遊ぶ』ことは、机の上の勉強と同じくらい、いや大人になってからは出来ないという意味では勉強以上に、大事なことだ」など、子どもの姿をもとに書いていました。八ヶ岳での活動と子どもの発達について、俵さんの本から考えさせられます。
《『ロゲイニング』》。3人1チームとなり、協力して地図に示された35個のポイントを1時間半内に回ります。ポイントの番号が得点になりますが、高いポイントは、わかりづらく難しい場所、スタート、ゴール地点から離れた場所にあります。地図を読む、地形を見る、方角を考える、3人が話し合ってどこから回るか作戦を立てます。地図を見ながらお互いにたすけ合って、判断してすすみます。
私は、昔の用水路44(下の写真)にいました。山の中にあって簡単に見つけられない場所でしたので、いったい何チームが来るのかと楽しみに待っていました。スタートの合図が聞こえ、しばらくして子どもたちの声が聞こえてきました。そして、私の予想以上の数のチームがこのポイントに来て、子どもたちの逞しさに驚きました。昔は用水路として使用され、高低差、段差があります。背の高い人が先頭に登って、後の2名の手をとって引きあげるなど、声をかけて助け合う様子などが見られました。

ここからは活動の様子の写真です。
〈火おこしをして、野外料理〉


〈夜の集い〉キャンプファイヤーのまきを運びました。そして〈夜の集い〉キャンプファイヤーを楽しみました。晴れた空には、北斗七星など、たくさんの星がよく見えました。


〈寮をきれいに掃除しよう!〉〈おいしい食事〉をいただきました


八ヶ岳の自然の中での活動によって、ドキドキわくわく感、励まし合いや認め合い、五感で感じ、考えたことなど、この合宿でも新たな八ヶ岳の魅力、発見がありました。60年以上前に生江義男先生が「高原寮に寄せて」に書かれた「語られざる詩」「見えざる絵」「聞こえざる歌」に出あえた喜びを感じました。
高原寮に寄せて 生江 義男
いまだ/この地には
語られざる詩がある/見えざる絵がある/聞こえざる歌がある
今日この日から/桐朋学園の若鳥たちは/新しい巣箱をおとずれ
天然の息吹に/とりくむのだ
八ヶ岳の山々は/瞬間の美をえがく
高原の草木は/盡く皆物言う
川俣のせせらぎは/妙なる調べをかなでる
そうだ/この地から この空から
若鳥たちは
原始時代の/あのすなおさを/ついばんでいくのだ
そして
それが/明日への/創造の糧となることを 1963年