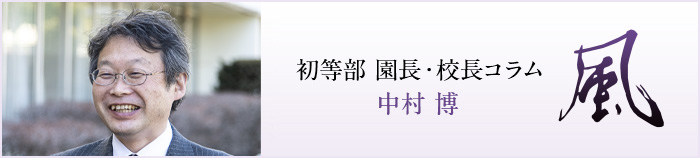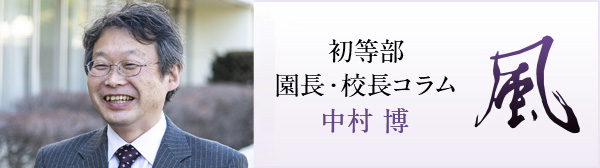園田青年会の皆さんとの繋がりを大切に [Ⅱ‐439]
金曜日の午後、沖縄から園田青年会の方がいらして、踊りを見せてもらいました。そして、一緒に踊ってくれました。ありがとうございます。


毎年、運動会の前に、園田青年会の方が来てくださり、三線の生演奏と響く歌声、「かっこいい」勇壮な踊りと声など、子どもたち、私たちを魅了します。
子どもたちにとって、すばらしい踊りを見る、一緒に踊る(踊ることができる)、アドバイスをもらうなど、心わくわく、どきどきする場となります。


園田青年会の皆さんの踊りを見ると、やりたい! に火がつく人がたくさんいます。腰を落とす、大きく腕を回す、ビシッと太鼓をたたく、大太鼓や締め太鼓の持ち方をかえる、大きな声を出す、声を揃える、声で自分と友だちを励ますなど、いろいろな変化が伝わってきます。


園田青年会の皆さんとの出会いは、1997年。
園田青年会の皆さんが、桐朋小学校の運動会で特別公演をしてくれました。それ以降、ずっと続けてきてくれています。
以前、園田の方に感想を聞いてみると、直前に一緒に練習する中で、「子どもたちが日々の練習でやってきた中のポイントで、リズムをつかむとか、三線、歌に合わせて太鼓を打つとか、改めて教えると、まばらだった太鼓の音が一つになってくる。それを子どもたちがわかると、また楽しくなる。太鼓を打つのが楽しい。それを打つときのエイサーのだいご味がわかる。」などと話してくれました。
また、「自分が1日前に行って一緒に踊る。このとき子どもたちも感じるんでしょうね。リズムに乗ったときの気持ちよさですね。一瞬、気持ちよさが伝わるというか、自分で体感できるというのがおおきいのかなあと思います。」とも。


その場にいる先生に聞くと、子どもたちが園田青年会の人たちと出会い、いっしょに過ごすことで、「大きな踊り、流れるような動き、大きなかけ声、そして体に響くしっかりした大太鼓と締め太鼓の音に、食い入るように見学します。その眼は、何かあこがれをもって見つめる眼差しのようです。」と感じたり、「自分たちの踊りを見てもらいアドバイスをもらいます。その後の踊りは、本当に見違えるほどです。集中の度合いがまるっきり違います。明らかに自分で意識して、腰を落とし、大きく腕を回してビシッと太鼓をたたきます。」などと、子どもの様子の変化を話してくれました。
今回は、園田青年会の皆さんとの繋がりについて書きましたが、今別荒馬保存会の方、中野七頭舞の保存会の方にも来ていただいて、たくさんのものをいただいています。皆様との出会い、つながりに感謝をしています。ありがとうございます。


子どもたちから、いつから民舞をやっているの? と聞かれました。調べてみると、
「1年生 荒馬」は、1985年~1994年と、2004年~2025年。95年からは違う踊りにも取り組みました。
「2年生 花笠踊り」は、2015年~2025年。
「3年生 桐朋みかぐら」は、1978年~2025年。
「4年生 ソーラン節」は、2020年~2025年。
「5年生 エイサー」は、1995年~1996年(東京エイサーシンカー)。1997年~2025年(園田青年会)。
「6年生 中野七頭舞」は、1983年~1994年(5年生で行いました)、1998年~2025年(6年生)。
でした。