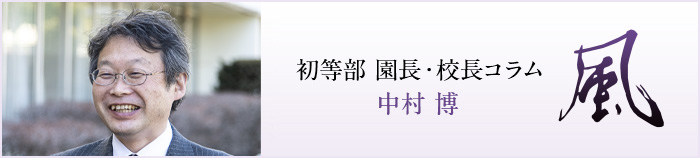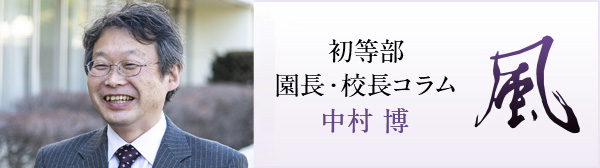いろいろな方に支えられて [Ⅱー420]
3月下旬、桐朋学園ご出身の東京慈恵会医科大学の方々にお会いして、学園との繋がりや日頃支えていただいていることへの感謝の気持ちをお伝えする機会がありました。

●2023年度、初等部教職員の研修会
岡部正隆先生(桐朋小のご出身。東京慈恵会医科大学副学長(解剖学講座 教授)*)より、『色覚の多様性とカラーユニバーサルデザイン~色覚が異なる人たちへの配慮と工夫』を学びました。**
ご講演内容は、〇「異常と言わない」色覚の呼称について、〇色が見える仕組み、〇色弱の人の色の見え方、〇色弱の人の頻度、〇色弱の人の色覚は劣っているのか、〇色弱の人は何に困るのか、〇カラーユニバーサルデザイン(CUD)、〇学校における配慮と指導、〇家庭での工夫 などでした。
ご講演より、「色覚は感覚の多様性の一つであり、血液型と同様、様々なタイプがあります。けれども、正常色覚とされる多数派の子どもと、色の見え方が異なるため、色覚の差異を超えて、子どもが同じように学べるようにするには、学校でも工夫や配慮が必要」だということを学びました。色の見え方が異なること児童がいることを前提に、違いを超えて同じに学べるよう、授業で図表などの表わし方、チョークやビブスを変えるなど、取り組みをすすめてきました。
教育現場で、『色覚の多様性とカラーユニバーサルデザイン~色覚が異なる人たちへの配慮と工夫』がひろがることを願っています。
*NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構副理事長。桐朋学園初等部同窓会Hp桐朋との繋がりVol.51~52 インタビュー記事掲載 **桐朋小学校Hpコラム「風」 初等部の『インクルーシブ教育』をつくるための学び合い[Ⅱー356]
●食物アレルギーによる事故
2012年、調布市内の小学校で、「食物アレルギーによるアナフィラキシーの疑い」で亡くなられた児童がいました。(調布市立学校児童死亡事故検証委員会報告書)その時の衝撃、悲しみ、そして取り組みの大事さなどを学んできました。
2022年、調布市が「食物アレルギー対策10年のあゆみ 事故が風化することのないよう、次の10年に向けて」として、再発防止の取り組みをまとめました。その中にはご遺族の「悲しみというものは時を経ても減ることなく、今も私たち家族それぞれの心の中に、当時のままに満ちております。」「折々の季節に遺してくれた、彼女のさまざまな言葉や表情を想う日々を、変わらず過ごしています。」「しかし一方で、年月を経るにつれ娘の存在が私たちだけのものではなくなり、社会のあちこちに痕跡を残し始めていることも感じています。」などと書かれていました。2012年に起きたことは、ずっと心に留めて過ごしてきました。
事故後、市内の園児、児童、生徒のアレルギー症状発症時の対応で、東京慈恵会医科大学第三病院の専用電話がつくられ、救急搬送の受入れ、アレルギー症状の判断等に係る相談ができるようになりました。
本校でも、食物アレルギーによるアナフィラキシーの疑い、心配のあった時には、ホットラインでご相談をさせていただき、対応することができました。
●2020年度以降、コロナ禍対応
学園の理事である薄井先生(東京慈恵会医科大学)に、コロナ禍の対応について、何回もご相談をさせていただきました。さまざまなご助言をいただき、コロナ対応をすすめることができました。
●2024年、東京慈恵会医科大学と桐朋学園の包括連携協定の締結
これまでの生徒の研究室訪問に加え、10月には岡部先生に「遺伝子カウンセラーについて」のご講演をしていただきました。このような学びもあって、東京慈恵会医科大学を志望する生徒が増えています。


子どもたちを守り、教育活動を支えてくださり、ありがとうございます。
写真は、しぜんひろば、園庭の様子から。今年も、同窓会の皆様よりいただいた枝垂桜が花を咲かせています。
下の写真は、子どもたちと行きたかった公園。