投稿者: tohoblog
ロマナ・ロマニーシンさんとアンドリー・レシヴさんの来校➄ [Ⅱ-368]
10月18日、毎日小学生新聞に、五味香織さんが書かれています。多くの新聞、テレビなどで、9月22日、桐朋小学校で行った授業を取り上げてくださり、戦争と平和を、命のかけがえのなさと尊さを感じ、考え、学ぶことの大切さを発信してくださることに励まされます。ありがとうございます。

以下、10月18日毎日小学生新聞、五味香織さんが書かれた記事を掲載させていただきます。
ウクライナの絵本作家が初来日 アートの力で戦争を終わりに 「戦争が町にやってくる」24の言語に翻訳
ウクライナに住んでいる絵本作家のロマナ・ロマニーシンさん(39)とアンドリー・レシヴさん(39)が9月、初めて日本を訪れました。二人が手がけた絵本「戦争が町にやってくる」(金原瑞人訳、ブロンズ新社)は、日本語を含む24の言語に翻訳されています。ロシアによるウクライナ侵攻が続く中、ロマナさんとアンドリーさんは日本の子どもたちと交流し、戦争と平和について語り合いました。
二人は、ウクライナ西部にあるリビウで暮らしています。来日中は約一週間にわたり、東京などで講演しました。東京都調布市の桐朋小学校では、約60人の6年生を前に、作品に込めた思いやウクライナでの日々を伝えました。
「戦争が町にやってくる」は、2014年にロシアがウクライナのクリミア半島に侵攻したことをきっかけにつくられました。ロマナさんは「戦争は遠い存在だったけれど、子どもたちにどう伝えるかを考えました。家庭で戦争のことを話してもらえるようにと思って描きました」といいます。
作品の舞台は、平和な架空の街・ロンドです。主人公のダーンカは、ガラスのように透き通った体を持っています。町は花であふれ、人々は歌を楽しんでいますが、そんな日常が突然、変わります。「戦争」がやってきたのです。/戦争は「黒くておそろしい」もので、「破壊と混乱と暗闇」を連れてきました。戦争が植えた雑草は、黒い花を咲かせ、大きく伸びて太陽の光をさえぎってしまいます。ダーンカたちは戦い、ある方法で平和を取り戻します。そして残ったものは―。
アンドリーさんは「主人公はデリケートで壊れやすい。でも、敵に向かう時には強くなります」と語りました。描かれた風景は、実際のウクライナの町がモデルです。表紙などに登場する赤いヒナゲシは、第一次世界大戦(1914~18年)で亡くなった人たちを追悼するシンボルだそうです。
作品は出版された2015年、絵本に贈られる国際的な賞を受賞しました。日本語版は22年2月にウクライナ侵攻が始まったことから翻訳されました。今年5月までに24の言語に翻訳され、世界に広がっています。
ロマナさんは、この作品を「将来への希望」と考えています。絵本をつくり続ける理由について、「私は兵士ではないけれど、アートという武器を持っています。アートで戦争を終わりに近づけたい」と力を込めました。

戦闘の中でも日常と笑顔を ウクライナの絵本作家 桐朋小学校で交流
ウクライナの絵本作家、ロマナ・ロマニーシンさん(39)とアンドリーレシヴさん(39)は、東京都調布市の桐朋小学校で6年生の児童約60人と意見を交わしました。二人はウクライナの町の写真を見せながら、戦闘が続く母国で創作活動を続ける意義を語りました。
警報でシェルターへ 町は日常的に攻撃にさらされているそうです。ミサイルの警報が鳴ると、人々はシェルターに避難します。警報が解除されたら帰宅して普段の生活に戻る、ということを繰り返しているそうです。/ロマナさんは、戦争が始まってから約半年間、怖さのため動揺が続きました。「食料がなくなり、水も飲めなくなるのではないか」と思ったことも。その頃に描いた動物は怖い表情をしていて「自分の怒りをぶつけているように感じました」と振り返ります。創作活動をやめた時期もありました。/二人が住むリビウの町では、建物などが破壊されると、その度に修復しています。元の姿に戻せるように、教会の窓のステンドグラスは撮影して記録を残しました。町中にある彫像は布で覆い、破片が飛び散りにくくしたそうです。
命は戻せない 話を聞いた後、子どもたちはグループに分かれて自分たちの意見をまとめ、二人に質問をしました。「作品を描く時につらくなかったですか」と尋ねられ、ロマナさんは「悲しかったり、心が痛くなったりすることはよくありました。友だちもこの戦争で命を落としました」と明かし、造り直せる建物などと違い「命は戻せない」と声を落としました。
ロシアの侵攻が始まった時の気持ちを聴かれたアンドリーさんは、「パニックになって逃げるのではなく、向き合うべきだと思いました」と語りました。現在、ウクライナでは戦闘に備えるため、大人の男性が自由に出国することはできません。アンドリーさんは、ウクライナの文化を世界に伝えるという目的で、特別に国の教科を得て来日することができたそうです。
本に触れるだけでも 二人は花を育てたりして、できるだけ平和な時と変わらない暮らしを続け、笑顔でいるといいます。創作活動を続ける難しさを感じたことはあるけれど、絵本をもってシェルターに避難する子どもたちを見て、「本は触れているだけでも落ち着ける存在だ」と大切さを感じたそうです。
交流を終え、児童たちは「戦争中でも、楽しみを見つけて日常を大事にしているのがすごい」「日本も戦争を繰り返してはいけない」と感想を語っていました。

10月18日、朝日新聞夕刊に「絵本を希望に アートは武器に」「ウクライナの作家 小学生と交流」という記事が掲載されました。
ヒロシマ平和学習1[Ⅱー367]
6年生広島修学旅行へ行ってきました。たくさんの出あい、触れあい、学びがあり、いろいろな方にたいへんお世話になりました。ありがとうございました。
〔平和公園での碑めぐり〕 6名のガイドの方に案内をしていただきました。爆心地すぐ近くのお寺へ行き、お墓のまわりを囲んでいる石を触わらせていただきました。ツルツルしたところと、高熱で一瞬で溶けそれが固まってザラザラしたところを触りました。爆風でひびやかけていたものを見ました。墓石に刻まれた命日が、昭和20年8月6日と書かれているものがたくさんありました。碑めぐりの後、じっくり向き合いたい場所でスケッチをしました。


〇世界の子どもの平和像(左上写真) 事前学習で行きたい場所を話し合い、ガイドの方にご相談して連れていっていただきました。世界の子どもの平和像も、その一つ。像には、核兵器のない世界のために/この像はヒロシマの子どもたちの/愛と平和のメッセージです/2001年8月6日建立 と書かれていました。


〇爆心地(左上写真) 当時の様子が写真と文からも伝わります。写真は、爆心地から見た北方の惨状の様子でした。写真下に、「原子爆弾は、この上空約600mで炸裂しました。爆心直下となったこの一帯は、約3000~4000度の熱線と爆風や放射線を受け、ほとんどの人びとが瞬時にその生命を奪われました。時に1945年8月6日午前8時15分のことでした。」と書かれています。
〔本川小学校平和資料館、平和記念資料館〕 開館前に並び、じっくり見学をしました。遺品や写真などから、「熱いよ」「水ちょうだい」「苦しい」などのうめき声が伝わってきます。「助けてあげられなくてごめんね」命を救えなかった悲しみや辛さ、苦しみも聞こえてきます。遺品や写真、絵、ガイドの方の話、文字などから、命の尊さを思いました。子どもたちの感想も聞いてあらためてまとめます。
資料館には、熱線をあびた瓦やびんに触ることのできる場所があります。熱線をあびた瓦は表面がつぶつぶの突起がありました。熱線をあびたびんは、曲がって固まっていました。実際に触ることによって、その強さ、衝撃を感じ、からだに残ります。

〔被爆証言〕 笠岡貞江さん(写真下)が話してくださいました。笠岡さんは、当時12歳中1の時に、爆心地から3.5㎞で被爆しました。右下の絵が当時の様子だそうです。お話では、お父さんのこと、お母さんのこと、ご家族のことなど、いろいろなことを話してくださいました。お話の中で、お母さんのことについてあまり触れられなかったので、終わった後でそのことを聞くと、怪我をしたお母さんが、自分たち子どもたちのことを大切におもう気持ちでいたのを思い出すと、話ができなくなってしまうと思って、ほとんど語ることができなかったとおっしゃっていました。
証言の最後に、2度と戦争をしてはいけない、と話をされていました。


〔宮島、厳島神社〕


〔大久野島〕瀬戸内海、島内めぐり、アクティビティ、毒ガス資料館


加害の歴史について話をしてくださった山内正之さん(下の写真)。お話のまとめで、「戦争は世界中の人間を不幸にする」、「歴史から学び、二度と戦争を起こさないようにしましょう」と言われていました。あらためてまとめます。


〇島内めぐり 長浦毒ガス貯蔵庫跡を見学しました。貯蔵庫跡前に設置された看板には、「旧陸軍は、1929年から終戦まで、この島でひそかにこの島で毒ガスの製造を行っていました。主な製品はイペリットとルイサイトで、いずれもびらん性ガスと呼ばれ、皮膚をただれさせる性質を持ち、年間生産量は多いときは1500㌧におよび、製造期15年の総生産量は6619㌧と言われています。」などと書かれています。今後、二度と戦争を起こさないために、加害の歴史も学んでいきます。
現在、わたしたちの世界では、戦争が起こり、続いています。戦争をやめること、平和を実現させていくことが課題です。ヒロシマでの学びをふり返り、まとめ、まわりの人に伝えるなど、課題に向き合います。


下校します
10月18日(水)14時45分現在、
京王線上下線ともに運転を再開しましたので、駅の状況を確認しながら児童を下校させます。
よろしくお願いします。
桐朋小学校 教務
京王線上下ともに列車がとまっています
13:29現在、京王線上り下り両方面で列車が通行を休止しています。
当該路線で、まだ下校していない子どもたちには、再開が確認できるまで学校に残るように伝えています。
運行が再開して下校を開始する際には、またお知らせいたします。
桐朋小学校 教務
ものの長さは〇〇でなんこ分?
2年生の算数では、水のかさに続いて、長さを学習しています。
最初から「定規」を使うのではなく、「㎝」「m」などの単位と人が出会うようになるまでの道のりを、実際に体験しながら学習していきます。


「238、239・・・」
ろうかでは階段の手すりを消しゴムで丁寧に測っていく子がいます。
「ちょっと、ここに寝てみて、〇〇くんなん人ぶんか測ろう!」
グリーンテラスでは、その横幅を寝そべりながら協力して測っていきます。
「花笠の幅は、鉛筆3本ぶんだった!」
教室の中では運動会に使った花笠を測る子もいます。

この日、それぞれの場所であれはどのくらい?とワクワクしながら測っていく子どもたちの姿がありました。
授業の終わり、
「でも〇〇くんと、〇〇ちゃんの鉛筆は違うから比べるってできるのかな・・・」
ある子がそう呟いていました。
この疑問が単位との出会いの始まりです。学びは続きます。
中野光先生に学び、考え合いたいこと [Ⅱー366]
2023年5月12日、中野光先生がご逝去されました。職員室の教育誌コーナーにある『生活教育』2023年10・11月号(日本生活教育連盟)では、中野先生の特集が掲載されています。
中野先生は、1954~1959年桐朋学園の教員でした。1955~59年、「初等部開設時の中心的役割」を担われました。応接室に創設メンバーの写真があり、中野先生も写っています。
 向かって右下が中野先生
向かって右下が中野先生
中野先生は、学生時代からジョン・ディーイを学び、その理論に共鳴し、「桐朋初等部創設にあたって、これから創られる学校のイメージをデューイを想いうかべながらあれやこれや構想する時と条件が与えられたことは、願ってもない幸せ」(『初等部誕生物語』)と述べていました。先生はデューイから、「子どもが構成し、創造し、そして能動的に探究するための作業所・実験室・材料・道具が、いやそういうことに必要な空間」、「伝統的な学校におけるカリキュラムおよび教育方法の画一」を変えることなどを学び、そうした考えを大切にして初等部を創ろうとされました。
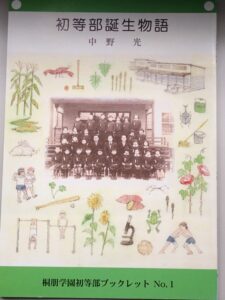
そのことは、初等部創立40周年(1995年)に寄せられた中野先生の発言からも伝わってきます。「私学としての桐朋はいわゆる『研究学校』(ラボラトリー・スクール)として発展していくほかないのではないか」/「教育の内なるものをゆたかにしたい、量より質で勝負する、というのがその存在理由だったはずです。ですからいわば教育の『質』を研究的に問いつづけるほかに発展の道はない、と考えるべきで、生江先生もそう考えておられたはずです」(『初等部誕生物語』)
先生は「質」について、「『いま』を大事にする教育」と述べています。ルソーの『エミール』に書かれた「子ども時代は再びめぐってはこないのだ。あてにならない将来のために、人々はなぜ、二度とめぐり来ることのないいまを犠牲になるのか」を引用し、「ここで学んだ者のすべてが『桐朋で学んでよかった』と思うことができる学園であってほしい」と期待を込めました。
「研究学校」については、「「私のやっている教育は果たしてこれでいいのだろうか」と疑う教師がいる学校、『もうすこしましにならないものだろうか』とみんなで問い直すことができる学校」と述べていました。
今、私たちは、中野先生に学び、「教育の質を研究的に問いつづける」園や学校の創造、「『いま』を大事にする教育」とは何かを考え、実践することなど考え合いたいと思います。
中野先生は、桐朋から金沢大学、和光大学、立教大学などの教員になりました。また、日本子どもを守る会会長、日本生活教育連盟委員長、日本教師教育学会会長、日本学術会議会員などを歴任されました。桐朋を辞められてからも、研究会やご著書などで、私たちを励まし続けてくださいました。
ご著書には、『初等部誕生物語』(桐朋学園初等部ブックレット)、『桐の朋 教育者・生江義男を読む』(私学公論社)、『教育空間としての学校』(中野光教育研究著作選集➀、EXP。著作選集は三巻)、『大正自由教育の研究』(黎明書房)、『もっと生かそう教育基本法』(つなん出版)、『子どもの権利条約ハンドブック』(岩波書店)他多数あります。
笑顔あふれる、桐朋小学校の運動会
先日、運動会が行われました。
4年ぶりに、ペナントが空高く上がり、コロナ禍以前に近い形で実施することができた今年。
ペナント準備や会場設営には、保護者の方々や卒業生をはじめ、たくさんのご協力をいただき、当日を迎えられました。


桐朋小学校の運動会は、ライン引きから用具の準備、司会進行、得点、救護、会場整理、応援、各競技の係…など、子どもたちが主体的に仕事を担い、土台から創り上げていきます。
その上で、一人ひとりが、今までの練習の成果を思いっきり発揮することができるのです。
プログラムは、〈民舞〉〈対抗競技〉があります。
民舞とは、『荒馬、花笠踊り、桐朋みかぐら、ソーラン節、エイサー、中野七頭舞』と、
学年ごとに伝統的な日本の踊りを表現発表するものです。


その中で、【中野七頭舞、市川直美さん、沖縄園田青年会、荒馬保存会、荒馬座】の方々には、練習から本番まで大変お世話になりました。
「太鼓の音が全然ちがう、お腹に響いてくる。すごい!」
「(踊る姿が)最高にかっこいい!」
「CDでなく、生の演奏を聴いて踊れたことに、感動した!」
本場の踊りを見て、音に触れ、そして直接教えてもらいながら、子どもたちの踊りはどんどん磨かれていきます。
上の学年の演技を見て、憧れを抱きながら、
「来年は、これをやってみたい!」と、見様見真似で踊ってみる下級生たち。
上級生は、自分たちが今まで踊ってきた民舞を懐かしむように、一緒になって踊る姿があちこちに見られます。
時には大人も一緒になって楽しむ…学校全体が一体となるその瞬間、その景色こそ、民舞の醍醐味なのだと改めて感じました。
対抗競技は、フェアプレー・ノーサイドの精神を大切に、みんなで励まし合い臨むこと。
「たくさん練習してベストを尽くせたから、悔いはない!」
「赤組も白組も最高のチームだったよ。」


勝ち負けだけに捉われるのではなく、失敗も含めて、お互いの頑張りを認め合う姿がそこにはありました。
そして最後、グラウンドには、みんなの笑顔があふれていました。
年に一度の運動会。
子どもたちがまた一つ、ぐっと成長する機会となったようです。
たくさんのご協力、ご声援をありがとうございました。
運動会の取り組みを振り返る[Ⅱ-365]
中野七頭舞、市川直美さん、沖縄園田青年会、荒馬保存会の皆さん、たいへんお世話になりました
それぞれの方が、美しい、しなやかな、力づよい、気持ちを込めた踊りを、私たちの目の前で見せてくれました。私たちのやる気を引き出し、ぜひあんなふうに踊ってみたい、踊りたいという憧れを育くんでくれました。ありがとうございました。
6年生の中野七頭舞の授業では、3回来校し、七名の踊り手の方が七つの踊りを見せて、一緒に踊ってくれました。ここがいいよ、こう踊るともっとよくなるよ、などと認め励まし、見本を見せてくれました。運動会前日、沖縄から園田青年会の皆さんと市川直美さんが来て、授業で踊ってくれました。放課後も一緒に踊ってくれました。太鼓がからだ全体に響き渡り、力づよさやかっこよさなど、いろいろなことに心をふるわせました。そして本番も一緒に踊ってくれました。市川さんは講師時代から40年以上、園田青年会の皆さんには25年間お世話になっています。荒馬保存会の小田切さんも、21年目の今年も大きな太鼓を打ちならし、子どもたちの踊りを見事に支えてくださいました。私たちにとって、宝物となる、とってもたのしい時間でした。


運動会で大切にしたい、育ってほしいと考えていること
●日常の集団活動を通して、その大切さを知ると同時に、全校児童が一同に会することの少ないので、全校児童が目的や行動を一つにして、喜びや楽しさを共有することを大切にしたい。
●児童・教員が様々な役割を分担、協力することにより、自覚的、自治的な力を獲得できるようにしたい。
●体育学習を通して獲得した技能や協働を充分に発揮し、それを達成した喜びを味わえるようにしたい。
●フェアプレー、ノーサイドの精神で、対抗競技に向かうことを身につけたい。
教員全員で、大切にしたい、育ってほしいという願いをもち、子どもたちにかかわり、新たな試みと試行錯誤をしながら運動会をつくっていきます。
人間、保育、教育に関して学ぶことの多い佐伯胖さんが、「文化的実践」ということを述べています。佐伯によれば、「文化的実践とは、よりよく生きるために、継承しつつ、創生しつつ、発展しつつ、変容しつつある人々の集合的な営みを特徴づけたもの」。運動会の取り組みは、よりよいものを模索して、味わい、さらによくしていこうとする試みと捉えれば、文化的実践と考えられるのではないかと思います。


運動会(私の感想)
2023年度の運動会は、4年ぶりにペナントが空高くあがりました。子どもたち、先生たち、おうちの人たちが協力して、できました。その景色は懐かしく、とてもいいものでした。3~6年生の大玉リレーでは、3、4年生が2人組で協力して大玉を転がし、5年生が4人組でバランスよく布を使ってすばやく大玉を運び、6年生が4人組で力を合わせて大玉を持ち上げて運ぶことをしました。コロナでできなかったことができるようになって、喜び合いました。
1人ひとりの係の仕事ぶり、たいへん良かったです。その仕事をやりとげていくことで、子どもたちが主役の運動会をつくっていました。
民舞や対抗競技では、これまでの取り組みの成果を発揮していました。一生懸命に取り組んだことを喜び、うまくいかない時には、お互い励ま合いました。そして、いろいろな学年の人たちをみて、「これ、やってみたい」などの憧れをたくさん育てていると思いました。
保護者の皆さん、いろいろな仕事、準備をありがとうございます。子どもたちへのあたたかい眼差し、声援をありがとうございました。
みんなで、いい運動会をつくることができました。ありがとうございます。


本日の運動会について
本日の運動会は予定通り開催します。
天候等の影響で多少進行時間が変わることもあります。
ご承知おきください。
・保護者は、入校証を見えるところに身につけてください。
・早すぎる来校はお控えください。
係の子ども達も、8時になるまでは校舎に入れません。
桐朋小学校 教務
運動会【民舞】 [Ⅱー364]
桐朋小学校の運動会は、前半は体育学習の成果の発表として民舞を、後半は赤白組による二色対抗競技等を行います。
運動会の取り組みを通じて、子どもたちの主体性を育てることを大事にしています。たとえば、開会式のエール交換では、応援係の人たちが考えた応援を1~6年生のチーム全員で行います。司会進行、整列、誘導、競技のリード、用具準備、ライン引き、他にも子どもたちが取り組み、運動会をつくります。4~6年の係の人たちの取り組みや各学年の民舞などをみて、「あっ、自分もやってみたい」など気持ちが動き、憧れを育てることも大切にしています。


係の人たちの様子
民舞について紹介します。全学年が発表します。古くから人々に伝えられてきた日本の踊りを表現します。
●一年生「荒馬」 青森県今別町の踊りで、ねぶた祭りの踊りがもとになっています。「ラッセラー!ラッセラー!」威勢のいい掛け声や太鼓のリズムに、一年生がたのしく駆けまわります。
●二年生「花笠踊り」 花笠音頭に合わせて踊る山形県の踊りです。自分たちで飾りつけした花笠を持って、元気な歌と掛け声に合わせて踊ります。
●三年生「桐朋みかぐら」 岩手県大森村に伝わる神楽舞を、踊りやすくアレンジしました。秋の豊作や幸せを願う気持ちがこめられています。日本の踊りがもつ独特の調子を味わいつつ、表現します。
●四年生「ソーラン節」 北海道ニシン漁をもとに創作された力強くキレのある踊りです。自分たちでつくった法被を身に着けて踊ります。
●五年生「エイサー」 沖縄本島や近隣の島々の盆踊りです。祖先の霊を供養し、無病息災を願い、家庭の繁栄を祈念します。桐朋小学校では、長年、沖縄市園田青年会の踊りを取り入れています。太鼓を打ち鳴らし「はやし」を入れながら、大地を踏みしめ、勇壮に踊ります。
●六年生「中野七頭舞」 岩手県岩泉町小本の中野地区で約180年前から踊られています。七つ道具を持ち、農地を開拓していきます。木を切り、畑を耕し、けものを追い払い、豊作を祝い、仕事の苦労をいやすというものです。大変難しい踊りに取り組みます。


3、4年民舞の様子
私たちが考える民舞
民舞は、民俗舞踊をもとにして、主に教育現場で教材として踊られてきました。その大もとの民族舞踊とは、日本各地で地域の祭りや盆踊り、神楽の奉納などで踊り継がれてきた芸能です。それらの多くは、日常生活の労働の中で培われてきた身体の使い方が、踊りの元になっています。
民族舞踊は、歴史的に地域の祭りなどの場で踊られ、地域の中で世代を超えて人と人を繋ぐ大切な共有財産、かけがえのない文化でした。人々は踊りを通して、繋がり合い、連帯し、生きる喜び、祈りや願いといった感情を共有しました。労働する農民などが生み出した本来の踊りは、たくましく、躍動感にあふれた全身的なものだったのでしょう。そのような踊りが、代々受け継がれる中で、力を効率よく使うことや合理的な動きになっていき、つまり「最小の労力で最大の効果」を発揮する、自然の理にかなった動きに洗練されてきたと思われます。日本の踊りは地を志向している。腰を安定させ、地に足をつけ、大地に根ざして労働し、生活してきた人々の身体の動きや所作とも関係するでしょう。
現代は、そのような労働が私たちの日常にほとんどなく、環境も生活も昔に比べ大きく変化しました。こうした中で私たちが見失ってきた身体の感覚を問い直す必要があると考えています。また、今私たちが感じる子どもの身体の変化、たとえば「体がかたく、ぎくしゃくした動き」、疲れやすく落ち着きがない、胸が閉じていて呼吸が浅いといったことも無関係ではないのでないかと考えます。
そこで、身体感覚をよみがえらせ、身体を耕していくことが、現代の私たちにとって必要と考えます。身体を耕したり、しなやかな身体をつくっていくために経験させたい動きの一つであり、教材であると考えます。そして、このような踊りを通して、自分を身体いっぱいに表現したり、その楽しさをみんなで共有し、繋がり合い、一つのことをつくっていく経験が、子どもたちの心に働きかけることも大きいと考えています。
長い時間をかけて人々に受け継がれてきた踊り、民舞を、子どもたちと踊ることの意味がここにあります。
*「桐朋小学校 体育集大成 ―民舞―」より


3~6年大玉リレー


