投稿者: tohoblog
空にはおひさま!
1年生のみなさん、入学おめでとうございます。
春らしい、とても朗らかなお天気に恵まれましたね。
おうちの方の手拍子にのって、5年生のパートナーと手をつないで第4体育室に入ってきたみなさん。
一人一人のお名前をよばれて、学校の印「校章」をいただきましたね。


これで、みんなは「とうほうっ子」になりました。
はやく一緒にべんきょうしたり、あそんだりしたいなあ、と先生たちも思いました。

それを一番願っているのは、きっと2年生です。
今日もたくさんの素敵なことを見せてくれました。
みんなもやってみたいものはあったかな?
コマ?けん玉?なわとび?
ネコちゃんみたいに、しなやかに体をうごかす体操や、かっこいい荒馬の踊りもありました。
歌も、詩も、2年生の声がとってもかっこよかったね。




♪空にはおひさま、足もとに地球、みんなみんなあつまれ、みんなで歌え!
(『ともだち賛歌』より)
素敵な友だち、たくさんの仲間と出会って、みんなで楽しく過ごしましょう。
今日は残念ながらお休みだったお友だちとも早く会えますように!待ってるよ!

(5年生はたくさん荷物運びをしてくれました。最後までおつかれさま!)
入学式でお伝えしたかったこと [Ⅱー339]
一人ひとりに校章を渡し、「おめでとう」を伝え、握手をさせてもらいました。全員に校章を渡した後、校章の由来や桐朋の名前に込められた願いなどを(以下のことを頭に描きながら)話しました。
校章は、「桐」が描かれています。桐は、本学園が1947年に「桐朋学園」として第二の出発をする際、指導と協力を受けた東京文理科大学、東京高等師範学校の校章に由来しています。一人ひとりを大切にする教育をしていくという願いを込めています。「朋」は、仲間という意味です。
桐朋小学校は、一人ひとりを大切にする学校にしたいと願い、その人その人が「やりたい」を大切にして、お互いの持ち味を大事にしながらみんなで育ち合っていこうという学校です。(※1)
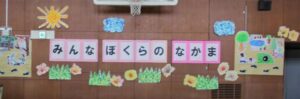
2年生、5年生、いろいろとありがとう! 写真はすべて入学式関連
保護者の皆さんに(次のことを頭に描きながら)お話しました。子どもたち、教職員は、今日をたのしみにしてきました。(朝、1年生の教室では、5年生が一生懸命に1年生に関わっていました。頼られることで、5年生は成長すると思います。)お子さんのご入学、おめでとうございます。
桐朋小学校は、《子ども一人ひとりを原点にした教育の実現》、《自分自身の人生の主人公となる、社会のつくり手となる根っこを育てる》ことを教育目標にしています。
その教育目標を実現するための11の柱(※2)から2つお話します。
1つ目が、学ぶってたのしい!です。今日の5年生パートナ―との出会い、友だちや先生との出会い、この入学式での2年生の表現(1年生に出会い、1年生に表現をすることで、2年生は成長すると思います。1年生は、2年生、5年生の成長する機会をつくってくれています。)などで、桐朋小学校で過ごすって楽しそうって思えたら嬉しいです。
11番目が、親と教員、親同士のつながりの大切さをあげています。保護者の皆さんとは、子どもの最善の利益とは何かをよく考えて、協働していきたいです。つながりという点では、本来、子どもたちはいろいろな人に見守られ、助けられ、安心して育っていきます。子育ては社会的な営みです。ところが、コロナでつながりをつくるのが難しくなりました。改めて、子どもたちが安心して育つために協働を。親と教員、親同士は、わからない、うまくいかないことも含め、お互いを大切に、つながっていきたいです。
保護者の皆様にとっても、節目となる日です。おめでとうございます。


(※1)学園の教育理念は、1947年教育基本法の精神「一人ひとりの人格を尊重し、自主性を養い、個性を伸長するというヒューマニズムに立つ『人間教育』」です。
(※2)1.学ぶことは楽しい! 2.子どもたちが共同で学ぶこと、働くこと、遊ぶことを大切にしています 3.子どもの自治的活動を大事にします 4.学びと同じように遊びを大切にします 5.私たちの教育はけっして急ぎません 6.子どもの発達にあわせた教育課程の自主編成教育を行います 7.実際に「行うこと」を追求します 8.遊びの過程や意味を大切にします 9.平和を希求し、一人ひとりの子どもが平和のつくり手として社会に参加できるような根っこを育てます 10.子どもが育つ環境をつくりあげます 11.親と教師、親と親は、子どもの教育のために結びあいます



新しい仲間を待っています
もうすぐ入学式!
新入生がやってくるのを学校中がワクワクしながら待っています。


6年生は、1年生の教室を掃除したり、入学式会場の設営を進めてくれました。
5年生は、パートナーとしての準備はもちろん、教室を素敵に飾ってくれました。
4年生は、入学式会場の装飾を仕上げてくれました。
3年生は、1年生のために、自分達の椅子を貸してくれました。
そして2年生は、学校を代表して歓迎の気持ちを伝えるために、連日体育館でお祝いの表現の練習をしていました。
明日は素敵な一日となりますように。

強い風が吹きましたが、なんとか八重桜は持ち堪えています。

正門脇の藤も満開です!
初等部説明会について
本校にご興味をお持ちくださるみなさま
5月13日(土)午後、本学園ポロニアホールにて
初等部(桐朋小学校・桐朋幼稚園)の説明会を行います。
園長・校長の中村博が初等部の教育についてお話しいたします。
受付開始は、4月24日(月)を予定しています。
詳細は4月20日以降に本ホームページでお知らせします。
お手数おかけしますが、ご確認よろしくおねがいします。
教務
新年度がはじまりました
2023年度がはじまりました。
濃いピンク色の八重桜が子どもたちを迎えてくれます。


クラス替えの発表があったり、教室のお引っ越しがあって慌ただしい一日でしたね。
緊張したり、わくわくしたり、おなかペコペコでおうちに帰ったことでしょう。
新しい教室、新しい仲間、新しい先生。
進級した実感がじわじわと湧いてくるのは、数日後になるでしょうか。
靴箱も移動しましたね。
明日の朝、うっかり前のところに行く人が何人かいるのではないかしら?
先生たちも、職員室の机の配置が変わって、とまどう場面がありますよ。
すこしずつ、新しい環境に馴染んでいきましょう。
今年度もどうぞよろしくおねがいします。




第4体育室での始業式の風景。それぞれの学年に、進級の拍手を送り合いました。
子どもたちとわくわくする活動や学びを [Ⅱー338]
初等部では、職員全員で新学期の準備をすすめています。子どもたちとの出会いをたのしみに、子どもたちと一緒に授業や活動をつくっていこうと、張りきっています。子ども(たち)が(と)夢中になる、もっとやりたい活動や授業を創り出していきます。私たち自身もわくわくする、自分の中に新しい世界を持てるようにと願って取り組みます。どうぞよろしくお願いします。
 4月7日、サトザクラが満開です
4月7日、サトザクラが満開です
●子どもたちと学び合う文化、教材づくりを
新学期に向けて「子どもたちとこんなことをしてみたいなあ」をたくさん考えています。子どもたちにぜひ出あってほしい文化、教材を吟味しています。教員自身もたくさん学んで、素敵な文化、教材と出あいたいです。
教員同士が、計画段階から話し合い、授業の計画を相談、共有し、実際の授業を見合い学び合うことを大切にしていきます。学年やブロック、学校として、協働して取り組みます。
●子ども(たち)の学びはどうかを大切に
「子どもの学びへの願い(わくわく、ドキドキ、夢中になどを大事に)や姿はどうだったか」、「学ぶことで、身の回りの世界の見え方やそれに対する関わり方が変わったのか」、「学びを通して仲間とつながっているのか」などを大切にすすめます。知識や技能が実生活で生かされている場面や、その領域の専門家の知を探究する過程を追体験し、「教科の本質」をもとに「深め合う」なども大切にしていきます。
●授業を見合い、お互いに学び合う
昨年度も、実際の授業や活動を見合うこと、子ども(たち)の姿から学び合うことを大切にしました。今年度も、活動や授業を見合うこと、子ども(たち)の姿からの学びを大切に取り組みます。
 1年生が育てたチューリップも満開です
1年生が育てたチューリップも満開です
学ぶことを、「知ってる」「私できる」で止まってしまう場合があります。学ぶってたのしい! もっと学びたい! 人と一緒に過ごすってたのしい! からだを動かすことがたのしい! など、「知ってる」「私できる」を超えていく豊かな活動や授業を創りたいと考えます。私たちが大切にしている試行錯誤や失敗も、学びを深めるために大事なことだと実感してもらう取り組みをしていきたいです。子どもたちの姿から、自身が変わることや、学びによって人とつながるなど活動や授業でどのように行われているのかなどを学んでいきます。
文部科学省の「児童生徒の問題行動」調査結果によれば、子どもたちの育ちの困難さが見られます。『感情コントロールに苦しむ子ども 理解と対応』楠凡之、丹野清彦著)では、「小学校低学年では、同一クラスに落ち着きがなかったり、感情制御の困難な子どもが何人もいるのがフツウの状態になってきている」などいくつもの事例がありました。
著者はその原因として、「大脳前頭葉の機能的な成熟と養育者との安定したアタッチメント(愛着―中村)の関係」の遅れを指摘。また、系列化の獲得による「自己形成視」(「過去に比べたら自らの成長に誇りをもって自覚するとともに、さらにいろんなことに挑戦してみたいという意欲を育んでいく力」と定義)が育まれていないことを指摘しています。他に、発達障がいの(疑い)子もいると書いていました。
対応として、「十分に遊びこみ、様々な活動を展開していく中で、子どもたちの自我・社会性の発達を保障し、結果として子どもたちが落ちついて学習や生活に取り組むための基盤を育てていく、回り道をいとわない教育実践が求められている。」(前掲書)とあります。私たちの学校、学級ではどうなのかを考えていこうと思いました。

保護者専用ページを更新しました
保護者専用ページを更新しました。ご確認をお願いします。
2023年度がはじまりました。どうぞよろしくお願いします [Ⅱー337]
3月の終わりに、1年間の振り返りをしました。そして、新年度のことを考えました。今年度は、平和な世界にしていきたい。生きる、育つ、守られる、参加するという子どもの権利が守られ、「一人ひとりが感情や意思を持った人間として尊重され、『なりたい自分』に向かってその子の可能性が最大限に伸ばされるよう応援してもらえるという、子どもの権利条約の考え」が大切にされる世界にしていきたいです。
 写真はすべて1年生が育てたチューリップ。
写真はすべて1年生が育てたチューリップ。
子どもに学ぶ
ロシアがウクライナを侵略し、1年が経ちました。3年生は、この内容に関連した小学生新聞を読み、考えました。その日の宿題を「この戦争について考える1日にしよう」と呼びかけ、子どもたちは自主学習ノートにTVなどで見たこと、聞いたことなどをまとめました。3月2日の通信にはその取り組み、子どもの表現などが書かれています。
せんそうについて思ったこと
ロシアがウクライナにしんこうして1年がたったらしい。
ぼくが8才だった時に始まって、もう9才だ。137㎝だったのに、143㎝にのびるくらい。ホームランが打てなかったのに、もう少しでホームランが打てそうだ。
1年間て、とっても長い。こんな長い時間、●●ちゃんと■■くんにとっては、きっと自分が何ができるようになったって考えるより、苦しいやかなしいやさみしい、こわいがいっぱいな1年だと思う。
ウクライナの人がせんそうで七万人は死んだと、ニュースは数しか言わないけど、この7万人は家ぞくがいて、家ぞくみんなが悲しい気持ちになったと思う。/その悲しい気持ちになった人の数は、どのくらいだろう。家族が4人いたとして、7万人の4倍の28万人。両親合わせて、さらに14万人。合わせて42万人。それだけの人を悲しませてしまったせんそうって何の意味があるんだろう。
たしかにぼくも人のものをほしくなっちゃうきもちはわかるけど、それを力ずくで取ることは人にいやなおもいをさせてしまうんだって、今のぼくはわかっているよ。
大人のロシアの国のせんそうを考えている人は、どうしてわからないんだろう。(学級通信3月2日号より)

作者は、ロシアがウクライナに侵略した一年間を自分の成長をもとに振り返り、桐朋小に来てくれた●●さん、■■さん(2人とも小学生)とお母さんのことを考えながら、「苦しいやかなしいやさみしい、こわいがいっぱいな1年だと思う」と想像し、表現しています。
戦争で亡くなった「7万」人から、それぞれに家族やつながりのある人たちがいることを考え、「それだけの人を悲しませてしまった戦争って何の意味があるんだろう」と問います。
それから、「たしかにぼくも人のものをほしくなっちゃうきもちはわかるけど、それを力ずくで取ることは人にいやなおもいをされてしまうんだって、今のぼくはわかっているよ」について、自分の経験と自分の変化を捉えていることが伝わります。経験や変化が自分にはある、だから「大人のロシアの国のせんそうを考えている人は、どうしてわからないんだろう」と問うのだと思います。
担任の先生は作者に向けて、「そのまっすぐな疑問を、大事なことを見失なった暴走する大人たちに問いたい」と応答し、心を響き合わせていました。作者は、一年間、応答される中で、信頼感や安心感を育み、作者自身が、自分は大切な存在なんだと感じられて表現していると考えました。
また、作者は文を書きながら、自分と他者やものごとを発見し、深める、疑問をもつなど、自分の気持ちや考えを自ら伸ばしています。
新しい日々へ
学校の桜は 満開です。
子どもたちに愛でてもらうことができず残念でしたが、思い返せば先日の終業日にはもうほころんでいました。

さて、2022年度が今日でおしまいです。
64期の卒業生からは、記念品としてベンチをいただきました。
図書室の前に展示していますが、オイルを塗って準備が整ったら校庭のメタセコイアの下に設置する予定です。
おしゃべりしたり、応援したり、ほっと一息空を眺めたり。みんなのお気に入りの場所がまた増えますね。
大切に使わせていただきます。


春は別れと出会いの季節。
これまでたくさんお世話になった方への感謝と新しい仲間に出会える期待が膨らみます。
これからも、みんなで素敵な桐朋小学校を作っていきましょう。


蚕の糸を紡ぐこと
前回の記事はこちら⇨「蚕研究プロジェクト」
蚕が大きくなり、
頭を八の字をかくようにふりだしたら、それは繭をつくるサインです。
大きくなった蚕は、少しずつ体の色が飴色になってくるのを確認しました。
繭をつくるお部屋「まぶし」を工作用紙で作って
サインを出してくれた蚕を入れていきます。


少しずつ、蚕の周りに糸が覆われていき
ついには見えなくなりました。
「さみしいなぁ〜。」
大きくなるのは嬉しいけど、毎日桑の葉っぱをとって一緒に生活してきたからこそ少し寂しい様子がありました。
蚕ががんばってつくった繭は、まんまるでとってもかたい。
その繭をお湯の中にいれて、糸がほどけてきたら細い細い何本かの糸をたぐりよせて
くるくると骨組みに巻き付けていきます。


蚕が繭を作った時と同じように、透き通るくらい薄い膜だったものが
何回も何回も回していくうちに、光沢をおびた糸の面に変わりました。

「つるつるだね!かたい!」
蚕の一生を学びながら、命のこと、歴史のこと、日本の産業のこととも向き合った三年生。
この蚕がくれたおくりものは、今年の美術展の学年看板にも展示して
来校したみなさんにみていただきました。
きっと一年をかけたこの学びが、4年生につながっていくのだろうと思います。







