投稿者: tohoblog
パートナーさんと学校探検その2
先週の木曜日、1年生と5年生のパートナー活動で学校探検を行いました。4月には校舎の外の探検をしたので、今回は校舎内の探検です。
5年生は実行委員を立ち上げ、1週間以上、毎日集まって準備を進めてきました。
今回の探検のテーマは「1年生クエスト」。1年生が勇者となり、いろいろな教室を回りながら、キーワードや最後のお楽しみワークショップで使う材料を集めていきます。




全部の場所を回れたら、最後は集めた材料を使って「しおりづくり」のワークショップ。シールを貼ったり絵をかいたりして、オリジナルのしおりが完成しました。
残りの時間はとにかく遊ぶ!しぜんひろばや第四体育室などで、体をいっぱい使って遊びました。


1年生を連れて歩く時や、遊んでいる時の5年生の優しい表情や手つき、とっても嬉しそうな1年生の姿が印象的でした。
学校のことをたくさん教えてもらった1年生。これからの長い学校生活で、自分だけのお気に入りの場所をきっと見つけていくことでしょう!
<5年生のふりかえり>
・今日、学校探検で一番うれしかったことは、パートナーがしおり作りのとき、ニコニコしながらえらんでいたことです。私のパートナーは、むらさきのひもに、紙は桐朋のマークがかかれているもので、シールはクローバーでした。できあがったのは1年生らしいしおりでした。すごくたのしかったし、パートナーもよろこんでいたのでうれしかったです。
・第二回学校探検では、最初こそ順調だったものの、絵画室でクイズに成功したのにシールを取るのを忘れてしまい、急いでパートナーといっしょにもどってシールを取ろうとしたら、Eもどこかの部屋でしおりの材料を取るのを忘れたのかしおりの材料を手でにぎって走っていて、僕以外にも材料忘れがいてほっとしました。
6年生八ヶ岳合宿 [Ⅱ-426]
5月21日~23日、山梨県北杜市にある桐朋学園八ヶ岳高原寮(標高1150m)で、6年生が合宿を行いました。お天気に恵まれ、予定していた活動をすべて行うことができました。たくさんの方にお世話になり、ありがとうございました。


主な活動は、自然の中の自由時間(余暇・余白を大事に)、ナイトプログラム、朝散歩(ネイチャーリーダーが、自然と触れ合える企画を考え、実行)、チャレンジプログラム、火おこしをして野外料理、夜の集い(リーダーに内容を任せる。アンケートをとり、話し合った結果、キャンプファイヤーとキャンドルサービスの合体版。点火の劇は4、5年生から続くシリーズもの)、大掃除(掃除当番表をケアクリリーダーが作成)などでした。ナイトプログラム、チャレンジプログラムでは、講師の甲斐崎さんにたいへんお世話になり、ありがとうございました。
この学年のテーマは、「やりたがる!」。4年合宿時の合言葉は「おもしろがる!」、5年合宿時の合言葉は「つながる!」。4年で培った「おもしろがる」精神と、5年からの「つながる」経験を生かして、6年は「やりたがる!」を合言葉に、自分たちでいろんなチャレンジをしていけることを願ってのものでした。「やりたがる!」には、「決められたり指示されたりするのではなく『任される』なかで合宿を自分たちでつくっていこうと思えること、自分自身にとってのチャレンジすること(自分のココロとアタマで自己決定をすること)、みんなのために動くこと」などの意味を込めていました(6年生の先生たち)。
最後の八ヶ岳、おもいっきり たのしもう!! という気持ちで過ごしました。


コラムでは、新たな試み《ナイトプログラム『ナイトアウェアネスウォーク』》と《チャレンジプログラム『ロゲイニング』》を取り上げます。自然豊かな場所で、自分に向き合い、仲間とともに、自然を味わい、冒険する内容でした。子どもたちとともに、「おもしろがる」「つながる」を大切にして、「やりたがる」気持ちを育むものであり、先生たち自身が学びながら、活動内容や方法を自由に創造的に組織していることの大事さに、私自身が学びました。
《『ナイトアウェアネスウォーク』》は、1クラス36名が、12名ずつ3チームに分かれて、寮の敷地の林の中に入ります。1(2)名ずつ灯りに向かって歩いていきます。下の写真は、ナイトアウェアネスウォークに向かう直前、寮内での様子です。

各グループで分かれ、真っ暗な林の中を進みます。スタート地点から、1(2)名ずつ約50m先の灯りを目指して歩いていきます。目印は先に見える灯りのみ。静かな森の中、手足の触覚、葉などに触れた時の音、聴覚などをたよりにすすみました。風の流れる感じや林の中の匂いもします。鹿の鳴き声も聞こえてきました。全員が灯りに辿り着いたところで、目印の灯りを消して暗くして見上げると、空が明るく見えました。昔の人たちは、こうした夜を過ごしてきたことも考えました。
*八ヶ岳からの帰りの電車で、俵万智さんの『生きる言葉』(新潮新書)を読みました。その中に、「自然の中で『めいっぱい遊ぶ』」があって、「(子ども時代は)五感を刺激されることで、成長してゆく時期」、「五感をフルに活用することは、言葉を鍛える土台のようなものではないか」、「『めいっぱい遊ぶ』ことは、机の上の勉強と同じくらい、いや大人になってからは出来ないという意味では勉強以上に、大事なことだ」など、子どもの姿をもとに書いていました。八ヶ岳での活動と子どもの発達について、俵さんの本から考えさせられます。
《『ロゲイニング』》。3人1チームとなり、協力して地図に示された35個のポイントを1時間半内に回ります。ポイントの番号が得点になりますが、高いポイントは、わかりづらく難しい場所、スタート、ゴール地点から離れた場所にあります。地図を読む、地形を見る、方角を考える、3人が話し合ってどこから回るか作戦を立てます。地図を見ながらお互いにたすけ合って、判断してすすみます。
私は、昔の用水路44(下の写真)にいました。山の中にあって簡単に見つけられない場所でしたので、いったい何チームが来るのかと楽しみに待っていました。スタートの合図が聞こえ、しばらくして子どもたちの声が聞こえてきました。そして、私の予想以上の数のチームがこのポイントに来て、子どもたちの逞しさに驚きました。昔は用水路として使用され、高低差、段差があります。背の高い人が先頭に登って、後の2名の手をとって引きあげるなど、声をかけて助け合う様子などが見られました。

ここからは活動の様子の写真です。
〈火おこしをして、野外料理〉


〈夜の集い〉キャンプファイヤーのまきを運びました。そして〈夜の集い〉キャンプファイヤーを楽しみました。晴れた空には、北斗七星など、たくさんの星がよく見えました。


〈寮をきれいに掃除しよう!〉〈おいしい食事〉をいただきました


八ヶ岳の自然の中での活動によって、ドキドキわくわく感、励まし合いや認め合い、五感で感じ、考えたことなど、この合宿でも新たな八ヶ岳の魅力、発見がありました。60年以上前に生江義男先生が「高原寮に寄せて」に書かれた「語られざる詩」「見えざる絵」「聞こえざる歌」に出あえた喜びを感じました。
高原寮に寄せて 生江 義男
いまだ/この地には
語られざる詩がある/見えざる絵がある/聞こえざる歌がある
今日この日から/桐朋学園の若鳥たちは/新しい巣箱をおとずれ
天然の息吹に/とりくむのだ
八ヶ岳の山々は/瞬間の美をえがく
高原の草木は/盡く皆物言う
川俣のせせらぎは/妙なる調べをかなでる
そうだ/この地から この空から
若鳥たちは
原始時代の/あのすなおさを/ついばんでいくのだ
そして
それが/明日への/創造の糧となることを 1963年


待ちに待った高尾山遠足
先週、5年生は高尾山へ遠足に行ってきました。
遠足の実行委員を立ち上げ、経路を確認したり、高尾山で見られる植物の絵をしおりに載せたり、様々な準備を進めてきました。各クラス9人の団を4つ作り、各団の実行委員がリーダーとなり、団会議も行いました。会議では、団の中でリーダー以外の役割(副リーダー、タイムキーパーなど)を決めたり、並び順を決めたりしました。
当日、目的地は高尾山の一丁平。去年も一丁平まで行きましたが、その時はケーブルカーを使いました。今年はケーブルカーを使わずに、2団18人のグループで登ることにチャレンジ。実行委員がリーダーとなり先頭を歩きます。18人の一番後ろには先生がつきましたが、「ペース大丈夫?」「ちょっと速いからゆっくりにして」など声をかけあいながら登っていて、とても頼もしく感じました。


300段もある階段の難所もクリアし、2時間ほどで一丁平に到着。
おいしいお弁当を食べ、そのあとは走り回って遊びました。(みんなさすがの体力!先生たちはくたくたで遊べませんでした…)
たっぷり遊んだ後は実行委員企画、「団対抗ゴミ拾い対決」。4年生の時にゴミの学習を行い、3学期終了間際に「ゴミ拾い遠足」を企画するも雨で中止。それもあって、今度こそはゴミ拾いをしたい!という思いから、遠足での企画を実現させました。


5分間、一丁平じゅうを歩き回り、全部でなんと480個もゴミを拾いました!一番多く集めた団は80個以上も。最初は「ゴミなんて落ちてないよ」と言っていた人もいましたが、まさかここまでたくさん集まるとは、先生たちもびっくりでした。
帰りはリフト乗り場まで1時間ほど歩き、リフトに乗って心地よい風に吹かれながら降りてきました。
グループで登るという初めての経験をし、7月の八ヶ岳合宿に向けての課題や目標も見えてきた遠足になりました。
みんなお疲れ様!
遠足に行ってきました。
3年生では、今年初めての遠足に行ってきました。
3年生になって初めてのクラス替えを経験した子どもたち。新しい環境にまだ緊張気味です。
今回の遠足ではみんなでたっぷり遊び、新しい友達とも仲良くなれたらと思っていました。
自由に登ったり、自由に作ったり、子どもたちは遊びながら、様々なものを学んでいきました。
帰りは、くたくたに疲れていましたが、後日書いた作文には
「ドロドロになったけど、たのしかった。」
「あんまり話したことなかったけど、〇〇君と仲良くなれた」
など、素敵な言葉をたくさん見つけることができました。
これからまだまだ長く付き合っていくみんな。どんな人なのかをもっと知って、伝えて、仲良くなっていけたらいいね。




ヨモギだんごづくり
2年生は、国語の学習で『春のくさばな』という説明文を学んでいます。「やわらかい ヨモギの めは、草もちの ざいりょうに なります。」という文があり、みんな口をそろえて、「「ヨモギ、たべたぁい!」」と大盛り上がり。手軽に作れそうなヨモギ団子をつくってみることにしました。新鮮なヨモギを探して見つけて、もりもりのヨモギが集まりました。


団子粉と水を合わせて、耳たぶくらいのかたさになるまで協力してこねこね。ヨモギをすりつぶすのも、ふたりがかりで力いっぱいに。意外とおさえる人が大事な役割なんです。すりつぶしたヨモギと、こねた団子粉を合わせてまたこねこね。


団子を好きな形にしたら、蒸し器でじっくりと蒸していきます。丸形、星形、ハート型など、個性あふれるヨモギ団子のできあがり。ヨモギの緑色を生かして、へび型にするのが大人気。きな粉をかけていただきました。「おいしい」「やわらかい!」「意外とヨモギの味はしないね」と、いろんな声が聞こえてきて、楽しくおいしく学ぶことができました。ぜひ、みなさんもおうちで作ってみてはいかがでしょうか。
2年生『みんなでつくった春の遠足』
5 月9 日(金)、待ちに待った遠足に行ってきました。先週2 日(金)雨が降ってしまい、9 日に延期することになってから「晴れるかな」「遠足行けますように」と遠足を楽しみにしている声がどのクラスからも聞こえてきました。てるてる坊主をつくって、教室の窓に飾っていた人たちもいたようでした。てるてる坊主で願いが届いたのか天気に恵まれ、出発することができました。
今回の春の遠足では「クラスをこえて学年でつながること」「子どもたちが中心になって行事をつくっていくこと」を大切にして準備を進めてきました。はじめて「実行委員」というものにもチャレンジしました。クラスから2 人ずつ代表が集まって、遠足のあそびを相談したり、当日の会の司会をしたり、クラスに戻ってスローガンを伝えたり・・・。とっても頼もしい6 人が準備をすすめてくれました。学校生活に慣れてきて、学校や仲間が自分たちのフィールドになりはじめた2 年生。だからこそ、自分たちでいろいろな工夫をしてほしいし、クラスの枠にとらわれず、いろんな人とつながってみてほしい。そんなふうに願っています。友達の輪が広がっていくといいなと思います。
前置きが長くなってしまいましたが、とにかく、2 年生は元気に楽しく府中の森公園へ遠足に行ってくることができました。

公園について学年のみんなでやる遊びは事前に各クラスでアイデア募集して、決めました。「こおりおに」、「木とりす」、「ふえおに」をしました。どの遊びも、クラス入り混じって楽しく遊びました。


お弁当やおやつも、色々なクラスの人が、しぜんと混ざったり、男の子ばっかり、女の子ばっかりではなく、いっしょに食べている人もいっぱい。 みんな、楽しくおいしく食べていました。おやつも、「こんなのもってきたよ!」と嬉しそうに見せてくれました。お友達と交換しないことやごみを落とさないで帰ってほしいことなど、大切なルールを話してありましたが、みんなしっかりやっていました。感心です。

自由遊びは、特別な道具な何もなし。それなのに、広場と森と友達がいるだけで、こんなに楽しい。子どもたち、遊びの天才だなぁと、改めて感じます。
帰りは方面別下校でした。東府中駅でコースごとに並びなおしてから、出発しました。2 回目だからか、上手になっていました。いつもの違う下校方法であっても、しっかりと話を聞いて帰路につくことができました。かっこいい2年生に成長していることを感じました。
評価に関わること [Ⅱー425]
土曜日もたくさんの方にお世話になりました。午前PTA総会でPTAの皆さん、午後掻掘りで56年生、保護者有志、同窓生の皆さん、ありがとうございました。美ら桐朋の皆さん、プレイルームでエイサー練習中にお邪魔しました。お会いできて嬉しかったです。


土曜午後、しぜんひろば委員の人たち、保護者の方、元委員同窓生の皆さん、ありがとうございました。
2025年は、初等部創立70年の年です。PTA総会では、活動方針テーマとして「70周年、手を取り合い、おもしろがってつくる楽しい桐朋っ子の未来」(運営部)、「Lets Enjoy70周年 心ひとつに桐朋っ子」(文化セクション)、「変わらない〔らしさ〕をつらぬく桐朋っ子~70周年!えいえいおー!~」(幼稚園部)、「~おめでとう70年~桐の子よ ゆたかに育て 根っ子から 伸ばし続けよ 笑顔の枝葉」(70年記念事業)などが出されました。それぞれの方のお話から、初等部をよりよくしていきたいという気持ちが伝わり、いっしょに一年間の活動、創立70周年の活動をつくっていきたいと思いました。どうぞよろしくお願いします。 (太字は中村。以下も同様)
私は、挨拶にかえて、創立70年を迎え、これまでの歴史から何をつかみとり、今につなぐのか、また現代の教育、社会にどのような意味と意義があるのを考えたいと思い、以下の➀~➃の視点でお話をさせていただきました。
➀PTA機関誌『わかぎり』1号(1955年7月発行)、2号(同年12月発行)より。1号(以下の写真)では『児童憲章』(1951年)全文、2号では『エミール』を掲載しています。児童憲章は、「児童は、人として尊ばれる」からはじまります。『エミール』(ジャン・ジャック・ルソー)では「子どもは自ら学ぶことが大好き」などを発見したことが書かれています。『わかぎり』を読みすすめると、創設時から「原点に子どもをおいた保育、教育の実現を」(私たちの保育、教育目標)願い、PTAで学び合うことを大切にしてきたことが伝わります。初等部創設メンバーの大場牧夫先生が、「いわゆる子どもの権利という側から考えたことに疎かった」ことに気づいて、「『児童権利宣言』『児童憲章』に保育の立脚点を置く」と言われており、このことを現在も大切にしています。(略)
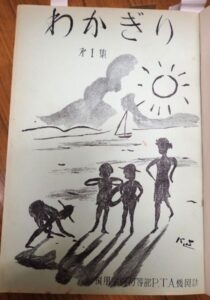
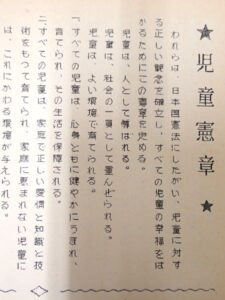
➁桐朋の原点は、1947年制定『教育基本法』―現代において、世界の平和を大切にすることはますます重要に。
1947年教育基本法は、「われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。」と書かれています。(略)
➂評価について―小学校、女子中高「通知表」廃止より
➃新園案内、新学校案内に込めたおもい(略)
今回は、➂評価について、を取り上げてみます。5月は、1回目の個人面談があります。
1)評価にかかわる歴史から
女子部門で「通知表」を廃止したのは、桐朋小が1963年、女子中高が1970年。
1956年、生江義男先生は、「成績評価というと、それは教育する者の最大関心事でありながら、過去60年、それを具体的に示しえたのが通知簿に過ぎなかった現実、私たちはそれを素直に認めねばならない。/教師は生徒の指導に全責任をもつものであるということはいうまでもない。しかしそれはただ学期毎にスタンプを押すことではなく、日々これあたらなる生徒個々への評価。しかもこれは明日の生徒指導の源泉となる評価でなければならない。」『わかぎり』4号(1956年)と述べています。
教職員で考え合い、大切にしたことは、
〇「いわゆる『学力』によって子どもを差別すべきではない。競争主義をとらない、一面的に子どもを見ない」。
〇「子どもの進歩の土台となるようなものを」たとえば、作品、レポート、テストなど、「その都度評価」を返す。評価には、「とくに、以後の学習の指針となることを盛り込むように工夫したい」(中高部)ということも。
〇子ども、保護者には、レポート、作品、答案などの「その都度評価」で連絡。また、学期ごとの個人面談によって、学習成果を知らせる。
〇「評点はどんな形であってもつけないこと」*評点だけを伝えて終えることはしないと受け止めました。


2)現在、私たちが「面談」で大事にしているいくつかのこと(小学校を中心に。それぞれの教員が大切にしていることを集めました。全てのことをどの面談でも行っているということではありません。)
・子ども、保護者との信頼関係づくりを重視する。
・ 保護者とは「その子を支えるための作戦会議」と捉え、共に考える姿勢を大切にする。
・学習、生活、友人関係、提出物について丁寧に伝える。
・ 子どもが自分で成長していけるような視点を共有する。
・ 学習面ではノートなどの具体物を使って説明し、点数に現れない表現力も伝える。
・その人の良い点を多く伝えることを意識している。
・ 子どもとの事前面談を実施し(特に高学年)、学習の理解度や努力を具体的に伝える。
・ 学校行事での姿や、探究的な活動の広がりも共有する。
・ 単元ごとにノートでの評価を実施。できないことではなく、前向きな姿勢や自己成長への気づきを評価している。
・ 面談前から子どもの様子を把握し、つまずきのポイントを明確にするためにテストの工夫を行っている。
・ 評価は見る人によって異なるため、多面的な視点を大切にしている。
・ 生活アンケートを保護者にも取ることもあり、有効に活用させていただいている。
・保護者に子どもの良さをプレゼンしてもらうこともあり、意図的に「認めて褒める場面」を設けている。
・ 「こんなに良いところがあるのに、こんな課題があるのはもったいない!」という形で伝えている。
・ 保護者との会話が弾むよう、座る位置にも工夫(斜めに配置)している。


3)評価と個人面談についてのメッセージ
私たちの学校には通信簿がありません。これは子どもを評価しないということではありません。その人らしさを認め、励ましていくことが評価だと考えます。
一人ひとりが自分の良さや課題を分かり自ら取り組んでいくことを大切にします。それにはとても時間がかかりますが、生涯の学びの姿勢につながります。
テストはその子の、そして私たち教師の課題を明らかにし共有していくためのものです。点数を上げるための勉強を繰り返すような『テストのための教育』をするような事はしません。
子どもの良さは数値で表すものではありません。
年に2回行われる個人面談が、親と教師が子どもの良さや成長を発見する大切な評価の場です。
2026年度学校説明会・体験会のお知らせ
2026年度学校説明会・体験会の日程を更新しました。
説明会、体験会はすべて予約制となっております。
予約開始の時期については、説明会の2~3週間前を目安にホームページページにてお知らせいたします。
説明会・体験会の日程は→こちらをクリック!←
本日のしぜんひろば池のかいぼりは、予定通り実施します。
本日のしぜんひろばの池のかいぼりは、この後の天気予報から判断し、予定通り実施します。
13時に理工室に集合してください。
参加予定だった方は以下の事項について、お子さんとご確認ください。
①雨上がりでコンディションが悪いので、無理はしないようにご判断ください。
②念のため、小雨対策でレインコート、ビニール袋を持ってきてください。その他の持ち物等は、先日のプリントを確認してください。
③当日欠席する場合は、必ず学校に直接お電話にて連絡してください。
よろしくお願いいたします。
消防車の写生会
先週、つつじヶ丘出張所よりポンプ車と4名の隊員の方を初等部グラウンドにお迎えして、恒例となった消防車写生会を行いました。
重さ20キロの防火服をまとい、ポーズをとっていただいたり、消防車のホースや、ポンプのバルブなど機器の説明まで丁寧にしてくださいました。子どもたちは興味津々で聞いていました。
絵を描き始めると思い思いの場所から、4年生は特に「立体」を意識して、細かいところまで丁寧に描き上げることが出来たようです。少し暑かったですが、とても有意義な一日になりました。









